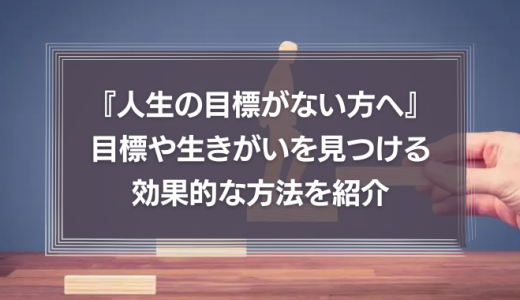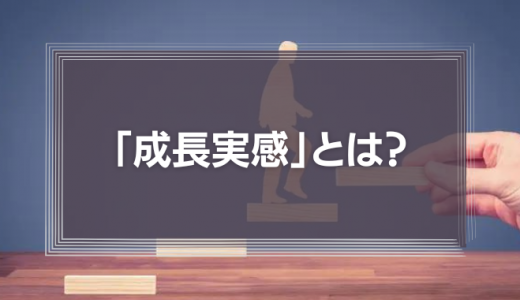労働者本人が始業時間と就業時間を決めることができる「フレックスタイム制」。ライフスタイルや働く人にとってのニーズの多様化を踏まえ、より柔軟な働き方の選択が可能となるよう、働き方改革関連法案の施行により2019年4月から改正されました。
厚生労働省の調査によると、既にフレックスタイム制を導入している企業は5.6%だそうです。(参考:厚生労働省・就労条件総合調査『平成31年就労条件総合調査 結果の概況』
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/19/dl/gaiyou01.pdf
今回は、フレックスタイム制の概要やメリット・デメリット、また導入する際のポイントや注意点について解説します。
目次
フレックスタイム制の基礎知識
フレックス(flex)とは、日本語で「柔軟な」とか「融通がきく」という意味になります。では、フレックスタイム制とはどの様な制度のことなのか、説明していきます。
フレックスタイム制とは
フレックスタイム制とは、決められた「清算期間」における「所定労働時間」の範囲内で、従業員自身が日々の始業時間や終業時間を決めることができる制度です。適用範囲は、全社共通だけでなく、部署単位や個人単位など、自由に設定することができます。
以前まで、清算期間は1ヵ月以内とされていましたが、現在は法改正により最大3ヵ月まで延長されました。また、所定労働時間は労使間の取り決めによって自由に設定することができますが、「法定労働時間の総枠(1ヵ月あたりの総労働時間の上限で、月の日数によって設定時間が異なる)」の範囲内である必要があります。
コアタイムとは
コアタイムは、「その時間内は必ず勤務していなければならない」時間帯のことです。必ず設定しなければいけないものではないので、もしも設定しなければ実質的に勤務日も労働者が自由に決めることになります(ただし所定休日は決めておく必要がある)。
また、コアタイムを設ける場合には労使間の協定によって自由に時間帯を決めることができます。たとえば、曜日によって時間帯を変える、コアタイム設定が無い日もある、ということも可能です。
フレキシブルタイムとは
フレキシブルタイムは、「労働者が自由に時間を決めて勤務する」時間帯のことで、その時間帯においては、出社時間や退社時間を都合によって決めたり、勤務開始後でも中抜けすることができます。
こちらも必ず設定しなければいけないものではなく、設定する場合には労使間の協定によって決められます。
(出典:厚生労働省『フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き』P.11
https://www.mhlw.go.jp/content/000476042.pdf)
フレックスタイム制のメリット
日本では初めて導入されてから約30年たつフレックスタイム制ですが、導入した場合のメリットについて確認していきましょう。
ワークライフバランスの向上
子どもや家族のケア、通院、資格取得のための勉強など、個人的な事情によって出勤や退勤時間を変えたいこともあります。
フレックスタイム制なら、自分の自主性と努力によってこれらが可能になり、個人の生活をより快適に・より充実させて過ごすことができます。プライベートと仕事のメリハリも付きやすくなるので、仕事に対するモチベーションの維持や作業の効率化にもつながりやすくなります。
通勤ラッシュでのストレスを軽減できる
国土交通省が公開している『東京圏における主要区間の混雑率』によると、朝の通勤ラッシュ時間帯の混雑率は平均163%、最高199%だそうです。約200%の乗車率というと、「体がふれあい相当な圧迫感がある」程度が目安と言われており、これでは通勤そのものがストレスの原因となってもおかしくありません。
フレックスタイム制によって時差通勤を可能とすれば、こうしたストレスは軽減することができるようになります。

(出典:国土交通省『三大都市圏の最混雑区間における平均混雑率・輸送力・輸送人員の推移』
https://www.mlit.go.jp/tetudo/toshitetu/03_04.html)
残業時間や労働負担の削減
フレックスタイム制は、個人の裁量によって勤務時間を自主的に調整できる制度です。同じ月でも月末月初などの仕事が多い日は残業する代わりに、仕事が少ない日や早く終わった日は早めに退勤するなどして残業時間を減らすことができます。また、夕方以降に仕事が長引く予定が分かっていれば、その日はゆっくり出勤するということも可能です。
この様に、従業員の自主性によって労働時間を効率的に使えば、残業時間のみならず、結果的には労働負担の削減にもつながります。
人材確保につながる
人生のステージによっては、結婚や出産、介護などで定型的な時間勤務が難しくなることも。その様な場合では、フレックスタイム制が導入されていることによって勤務継続がしやすくなり、離職防止に役立ちます。
また、自主性があり自己管理能力の高い優秀な人にとっては、フレックスタイム制が導入されている職場は効率的な働き方のできる魅力的な職場に感じられます。そのため、人材確保のためのアピールポイントにもなります。
<<あわせて読みたい>>
メタバースとは?メタバースの語源や意味、具体例をわかりやすく解説!
DXとは?なぜDXと略すの?デジタルトランスフォーメーションの意味や定義をわかりやすく解説
フレックスタイム制のデメリット
柔軟な働き方が可能になるフレックスタイム制ですが、デメリットも存在します。
就業規則の変更が必要なため導入までに時間がかかる
フレックスタイム制を導入するためには、就業規則の変更とそのための取り決め事項を労使間で協議の上決定する必要があります。その他にも、フレックスタイム制の適用業務範囲やコアタイムの適切な範囲など、事前の検討事項も多いため、これから導入するという場合には十分な期間をかけて実施しなければなりません。
社員同士の情報共有やコミュニケーションが取りづらい
出退勤の時間が社員間でバラバラになりやすく、会議や共同作業などの時間調整が面倒になったり、用があるのにまだ出社していない、といったコミュニケーションロスが発生しやすくなります。
かといってフレキシブルタイムを短くしてしまえば、フレックスタイム制としてはそぐわなくなってしまうため、コアタイムの確定をする際には現実に即した時間帯をよく協議した上で決定する必要があります。
外部取引先との連携に不備が出やすい
取引先の就業時間と自社の社員のコアタイムに大幅な乖離があるような場合には、「担当者が全然つかまらない」、「対応が遅い」と言ったクレームにつながる可能性もあります。また、緊急事態なのに担当者がいないと対応できないとなれば、大きなトラブルになりかねません。
そのため、取引先に対しても自社のコアタイムをアナウンスしておく、担当者に直接連絡がとれる携帯電話を支給する、担当をチーム制にする、などの対策も取っておくと良いでしょう。
自己管理が苦手な従業員が多いとルーズな働き方になる
フレックスタイム制は、あくまでも自由度の高い出退勤時間が選べるというだけで、タスクの終了をいつまででも伸ばせるわけではありません。しかしながら、あくまでも自主管理にゆだねる部分が多く、自己管理が苦手な従業員は時間管理がルーズになることもあります。
「フレックスタイム制になったら生産性が下がった」というケースもあるため、勤怠や進捗管理の方法もあわせて検討する必要があります。
フレックスタイム制に対応できる職種や部署が限られる
他部署や取引先などからの連絡に対してすぐに対応しなければならない業務を行っている場合や、複数の業務やプロジェクトに兼務している場合には、フレックスタイム制の導入は難しくなります。
逆に、タスクや成果物をベースに作業管理が可能な業務では、フレックスタイム制は導入しやすくなります。
同じ会社でも職種や部署によってフレックスタイム制の導入有無が異なると不公平感が出てしまうこともあるため、社員の理解を得ることや配置換えなどを考慮する必要があります。
フレックスタイム制における残業代について
フレックスタイム制においても、残業代(時間外手当)は支払う必要があります。ただし、定刻勤務の場合とフレックスタイム制では、以下のように残業時間の考え方が異なります。
| 定刻勤務 | フレックスタイム制 |
| ・法定労働時間(1日8時間・週40時間※)を超えたら残業
※週44時間となる特例事業もあるが、ここでは説明を省きます |
・清算期間における総労働時間が所定労働時間を超えたら残業
・清算期間が1ヵ月を超えた場合 (1)清算期間全体の労働時間が週平均40時間を超えたら残業 (2)1か月ごとの労働時間が週平均50時間を超えたら残業 |
定刻勤務の場合に比べると、フレックスタイム制の場合には少し複雑な条件となります。ポイントは次のような点です。
<フレックスタイム制のポイント>
- 清算期間ごとに残業時間のカウントをするため、法定労働時間を超えて勤務したとしてもその時点では残業代が発生するかどうかは確定しない
- 1日あたりの所定労働時間に満たない日があったとしても欠勤扱いとはならない(賃金控除もされない)
- 清算期間が1ヵ月超~3ヵ月未満の場合には、残業代のカウント条件が増える
フレックスタイム制では、精算期間における総労働時間が所定労働時間に対して超過していれば残業にカウントされますので、残業時間の計算式は「総労働時間-所定労働時間」です。
- 総労働時間の過不足は繰り越せる?
もしも総労働時間が所定労働時間よりも不足していた場合には、その分を賃金から控除するか、不足分を次月に繰り越して所定労働時間と合算する方法があります。ただし、不足分を繰り越してしまうと長時間労働をしなくてはならなくなってしまう可能性もあるため、就業規則等によって繰り越し期間に制限をもうけることもあります。
では、残業に該当する超過時間分を繰り越して次月の労働時間で相殺し、残業代が発生しないようにすることはできるのかというと、それはできません。必ず該当する月の賃金で精算する必要があります。
- 法定内残業と法定外残業
また、残業時間には「法定内残業」と「法定外残業」があります。違いは、発生した残業時間が法定労働時間の総枠を超えない部分なのか、超えている部分なのかです。
たとえば、「所定労働時間<総労働時間<法定労働時間の総枠」という場合には、法定労働時間の総枠に残業がおさまっているので、法定内残業となります。
次に、「所定労働時間<法定労働時間の総枠<総労働時間」の場合には、法定労働時間の総枠を超えない時間分は法定内残業となり、超えた時間分は法定外残業となります。法定外残業の時間分に対しては、労働基準法に従って残業代の「割増賃金」を支払う必要があります。
もしも「所定労働時間=法定労働時間の総枠で、かつ所定労働時間<総労働時間」という場合には、法定内残業時間はありませんので、全ての残業時間分が法定外残業となり割増賃金対象となります。
フレックスタイム制を導入する際のポイント
フレックスタイム制を導入する際のポイントを解説します。
フレックスタイム制について労使協定を締結する
フレックスタイム制を導入するためには、労使間で協定を締結する必要があります。必ず定めなければならない項目は次の6項目です。
- フレックスタイム制の適用範囲
- 清算期間とその起算日
- 清算期間における総労働時間
- 標準となる1日の労働時間
- コアタイム
- フレキシブルタイム
もし清算期間が1ヵ月を超過する場合には、さらに所轄の労働基準監督署長への届け出が必要となり、これを怠ると30万円以下の罰金が科せられることがあります。
協定締結が必須の6項目について、ポイントは次のとおりです。
- フレックスタイム制の適用範囲
対象となる従業員の範囲このことで、全社員でも特定の部署のみでも、個人、グループなど、自由に設定できます。
- 清算期間とその起算日
従業員が労働する時間を定める期間とその起算日を決定します。期間は1ヵ月~3ヵ月の範囲で、閑散期や繁忙期のサイクルなどを考慮して決定することができます。
- 清算期間における総労働時間
清算期間において従業員が労働しなければならない時間、つまり所定労働時間を決めます。清算期間単位で法定労働時間の総枠以下の時間にしなければなりません。決め方は、「清算期間において〇時間」という決め方の他、「1ヵ月〇時間×〇ヶ月」、「1日あたり〇時間×〇日」というような決め方ができます。
- 標準となる1日の労働時間
清算期間における所定労働時間を同期間の所定労働日数で割った時間のことで、有給休暇取得時には、この標準時間を労働したとみなしてカウントされます。
- コアタイム
従業員が必ず労働しなければならない時間帯のことで、決めなくても問題はありません。コアタイムを無くして出勤そのものを自由とすることもできますし、曜日や日付単位の設定や、時間帯も日によって変えることができます。
- フレキシブルタイム
従業員が自主的に選べる出勤・退勤可能な時間帯のことで、必ずしも決めなくてもよい項目です。決める場合には、フレキシブルタイムの開始時刻と終了時刻を決めておきます。
フレックスタイム制を労働条件とする
会社が従業員を採用する際には、労働条件を明示した契約書を書面で取り交わす必要があります。いわゆる「労働契約書」や「雇用契約書」というものです。
この契約の中で明示しなければいけない項目には、雇用期間や就業場所、始業や終業時刻、賃金、退職手当などに関する項目があります。つまり、フレックスタイム制を導入した場合には、契約書にそれを労働条件として明示する必要があるのです。
フレックスタイム制を導入している場合に明示すべき項目としては、フレックスタイム制であること、フレキシブルタイムとコアタイムの開始時刻と終了時刻などになります。
厚生労働省がサンプルを公開していますので、こちらをひな型にして作成することもできます。▶厚生労働省『労働条件通知書』サンプル
フレックスタイム制を導入する際の注意点
フレックスタイム制の導入にあたり、いくつか注意すべき点がありますので、そちらも解説します。
コアタイムを設ける場合は前後にフレキシブルタイムを設ける
コアタイムを設定する場合には、前後に必ずフレキシブルタイムを設ける必要がありますが、その内容は適切でなければなりません。
たとえば、フレックスタイム制と言いつつ、フレキシブルタイムが極端に短い場合や、コアタイムの開始~終了までの時間がほぼ1日の所定労働時間に等しい場合、始業したら1日あたりの所定労働時間にほぼ等しい時間を必ず勤務しなければならないとしている場合などは、フレックスタイム制とはみなされません。
18歳未満の場合はフレックスタイム制は導入できない
18歳未満の従業員に対しては、厳しい労働条件の下で労働させることが無いように、一部の労働基準法が適用されません。具体的には、労働基準法第60条の規定によりフレックスタイム制と一部の変形労働時間制については導入することができません。そのため、年少者を従業員として雇い入れる場合には、その他の従業員と同一の労働条件の契約で問題がないかどうか注意が必要です。
フレックスタイム制でも休憩時間は必要
フレックスタイム制だからといって、労働基準法第34条の規定に従い、1日6時間を超える労働に対してはコアタイム中に休憩時間を与える必要があります。ただし、別途労使協定を締結すれば、従業員の判断に委ねるとすることもできます。
まとめ フレックスタイム制をうまく取り入れることが重要
フレックスタイム制は、働き方改革の一環としてワークライフバランスを向上し、仕事の効率化やモチベーションアップにつながるというメリットがあります。
その一方で、社内外とのコミュニケーションロスを起こさないような配慮も必要になり、業種や職種によっては導入が向かないケースもあります。
フレックスタイム制の導入にあたっては、本当に導入効果はあるか、効果的な制度内容はどの様なものかなどをよく検討し、上手に取り入れることが重要となります。
参照
厚生労働省「フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き」
https://www.mhlw.go.jp/content/000476042.pdf
厚生労働省「採用時に労働条件を明示しなければならないと聞きました。具体的には何を明示すればよいのでしょうか。」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_4.html
厚生労働省・就労条件総合調査「平成31年就労条件総合調査 結果の概況」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/19/dl/gaiyou01.pdf))
国土交通省「三大都市圏の最混雑区間における平均混雑率・輸送力・輸送人員の推移」
https://www.mlit.go.jp/tetudo/toshitetu/03_04.html)