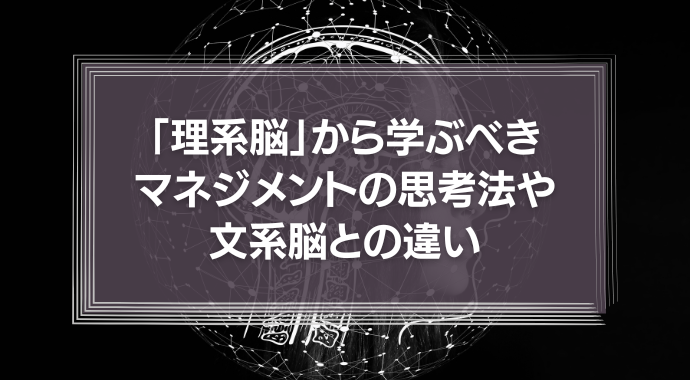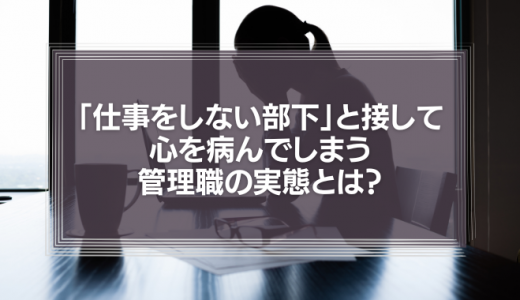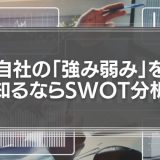理系の人材は、時代を問わず企業経営者から安定した評価を受け続けています。
ITや建築に直接関わる工学部生、というイメージがあるかもしれませんが、そうでなくても基本的に「理系脳」「数学脳」を持っている人材は、同じことであっても「文系脳」の人材とは違った切り口で物事を考える訓練をしているので、無理もないことでしょう。
結論が同じであったとしても、脳内のプロセスは非常にシンプルかつ合理的で独特なものがあり、こうした考え方が戦略やマーケティングに役立つからであると、一つの仮説を置きたいと思います。
数学、というと拒否反応を示す方もいらっしゃると思いますが、そんな仮説を証明して行きたいと思います。
<<あわせて読みたい>>
目次
「理系脳」の大きな特徴
理系脳をもつ人が物事を考えるとき、いわゆる「文系脳」と大きく異なる点はこのようなものです。
・逆算の発想を持っている
・最短距離で本質にたどり着こうとする
・仮説を立て、すぐに行動に移すことを重要視
・リスクは伴って当然と考える
それぞれの概念と、ビジネスシーンでの応用例を紹介していきます。
<<あわせて読みたい>>
「因数分解」から始まる逆算思考
筆者はガチガチの理系学部出身です。
「理系脳」「文系脳」に、「生まれながら」はありません。その思考方法は、知らぬ間に訓練されて身についたもの、とも言えます。
そこには、数学的思考が大きく影響します。
まず、「因数分解」です。嫌な響きに聞こえる人もいるでしょうが、ビジネスの世界では重要な概念であり、読者の皆さんはもはや「x」や「y」が出てくる方程式を覚える必要はないと思いますので、簡単に説明します。
因数分解とは「掛け算の逆算」です。
掛け算の結果から、何と何を掛け合わせたのかを推測する行為です。
ここで軽い脳トレをしてみましょう。
「6」という数字は、何と何の掛け算でできているでしょうか?
6=1×6
6=2×3
です。「6」という数字を構成する「因数」に分解するとこのようになります。
では、「16」という数字はどうでしょう。
16=1×16
16=2×8
16=4×4
です。2の4乗、という人もいるかもしれません。
実は、因数分解とは、その概念はたったこれだけのことです。
しかしこれを、ビジネスシーンで使っている人はどのくらいいるでしょうか。
例えば、プロジェクトの過程で「16」の量の問題が起きたとします。
原因を取り除こうとするとき、どのように考えるでしょうか?
16-1-1-1-1-1… =0
と考えてしまってはいないでしょうか。
これだとまず、16の要素を探して、その後16回も引き算をしなければなりません。
16人以上で会議をしなければならなくなります。
これが、500だったらどうなるかと考えると、恐ろしいものがあります。
引き算をしているうちに、環境は変化しているでしょう。
「因数分解」をする理系脳は、こんな考え方はしません。
2つ、せいぜい3つの因数に物事を分解します。それ以上の数の要素は作りたくありません。
ピタリと割り切れなくても、「近似値」で良しとします。
このように、最初の段階では問題を2つか3つくらいの「かたまり」に分けて考えれば、第一段階としてはせいぜい2つ、3つの部門長とだけ話をすれば済みます。
合理性重視なのです。
ビジネスで言えば、例えば、商品の売り上げが悪かったとしましょう。
「なぜ」「何がいけなかったのか」、たくさんの要素が頭に浮かぶことでしょう。
しかし、理系脳の脳内ではこのような因数分解が始まっています。
売り上げが伸びない=(商品の魅力がない)×(売り方が悪い)
この場合は、同業他社の製品との比較、ニーズといったものが「商品の魅力」です。
そして「売り方」は、価格やターゲット設定、広告、販売場所、ということになります。
そして、この2つの要素のどちらが2で、どちらが8なのかを定量化していますから、「誰と」「どのくらい」話をすれば良いかも把握しています。
そして定量化、といっても、それも特段難しいことではありません。
交通事故を起こした時に、自然と過失割合を考える人が多いと思いますが、それを思い出すと良いでしょう。
「こんな状況だから、相手が8割くらい悪いだろう」と推測するのに似ています。どちらの過失がいくつで、どちらの過失がいくつか、という風に、要素が頭の中で「2つ」におのずと集約されています。
このとき、何を根拠に「8割」相手が悪い、と考えていますか?
経験や知識ではないでしょうか。
理系脳は様々な場面で、知識や過去のデータを元にこうした「過失の定量化」をしているのです。
また、こうした因数分解の過程で、「気持ち」「努力」は要素に入れていません。
交通事故の場合では、
「ハンドルを切ろうと思ったのに」と言われても、切れなかったから事故になったのであって、「気持ち」は結果とは無関係、そう考えますし、事故は実際そのように扱われます。
努力や気持ちが無価値だと言っているわけではありませんが、最初にそれを持ち出していたのでは膨大な足し引きをしなければならなくなり、その作業量を嫌います。
<<あわせて読みたい>>
逆算思考が必要な理由
ドラッカーがマーケティングについて語る時、必ず言及するのが、「顧客からスタートする」ということです。
「エッセンシャル版マネジメント」には、以下のように綴られています。
”真のマーケティングは顧客からスタートする。すなわち現実、欲求、価値からスタートする。「われわれは何を売りたいか」ではなく、「顧客は何を買いたいか」を問う。
「われわれの製品やサービスにできることはこれである」ではなく、
「顧客が価値ありとし、必要とし、求めている満足がこれである」と言う。
…マーケティングが目指すものは、顧客を理解し、製品とサービスを顧客に合わせ、おのずから売れるようにすることである。”
[1]_p17
何かを売ろうとするとき、「自社にある複数のリソースをどう掛け合わせて新しいものを作るか」という考えになってしまってはいけない、ということです。
この場合、「自社のエゴの押し付け」になってしまいます。長らく日本企業が陥り続けている状態です。
これに対し、「逆掛け算」の世界では、「世の中の顧客のニーズを満たすには、自社のどのリソースをどのように、いくつずつ掛け合わせれば良いか」と考えるのです。
このような意味で、「逆算思考」は理にかなっています。
しかし、理系脳の「逆算思考」は、問題を解明するための「最低限のツール」でしかありません。
<<あわせて読みたい>>
「最短距離」という信念
理系脳は常に、物事の本質にいかに「最短距離」でたどり着くかを考えています。
少ない情報から本質を見つけ出し、逆算能力をフルに発揮するのが「微分積分」です。
これもまた、嫌な響きに聞こえる人も多いことでしょう。
筆者の大学受験での数学の試験は、180分でたったの6問、という構成でした。
全ての問題は3~5行程度の文章だけで与えられる、いわゆる「証明問題」で、そのほとんどが微分積分に基づくものです。
「結果がこうなることを証明せよ」です。
与えらえるのは日本語数行、という限られた情報、結果のみです。
少ない情報から法則性を見出して本質を探し出し、そこから自分の経験に基づいて、結果へ向かった議論を展開していくのです。
「結果がこうなること」=「なぜこうなったのか」という思考は、ビジネスにおいても必要です。
しかも、「結果」というのは、見える部分だけでは全ての答えを与えてくれるものれはありません。
そこで、情報の欠片に自分から積極的にアプローチし、なんとか方向性と法則性を見出そうと考えるのが理系脳です。
ビジネスでも同じでしょう。他人が情報を与えてくれるのを待っていては、世のスピードにはついていけません。
そして、その際に一つの「目安」を持っています。
証明問題を説いている過程で、計算量のやたらと多い、複雑な数式をやたらと並べなければならない泥沼のような所にはまりこんでしまうと、「このやり方は良くないな」とすぐに気がつきます。
多くの話はシンプルであり、回答は短ければ短い方が良い、と経験で知っているからです。
それは、ビジネスの世界では、物事の説明のしかたに直結します。
問題を共有するとき、「あれも要素、これも要素」とズルズル引きずるのではなく、シンプルな法則性を示し、「このような傾向があるようだ」と、まず方向性を示すことは非常に大切です。
ドラッカーの言うところの「管理手段」に似ています。
ドラッカーは、あらゆる管理手段が、七つの要件を満たさなければならない、として
“
①管理手段は効率的でなければならない。
②管理手段は意味あるものでなければならない。
③管理手段は測定の対象に適していなければならない。
④管理手段の精度は、測定の対象に適していなければならない。
⑤管理手段は、時間間隔が測定の対象に適していなければならない。
⑥管理手段は単純でなければならない。
⑦管理手段は行動に焦点を合わせなければならない。 “
[1]_p167-170
と綴っています。
<<あわせて読みたい>>
制限時間とリスクの間で
また、このような訓練に晒されてきた理系脳は、「リスク」の感覚も独特です。
先の試験の話の続きですが、泥沼のような道が見えた時、対処の仕方は2つです。
ひとつは、全く別方向からのアプローチを探すことです。
もうひとつは、「間違いではない」ということはわかっているので、ゴリ押しで計算を進めることです。
どちらを選んでも正解にたどり着くことはできるのですが、どちらを選んでもリスクが存在しています。
前者の場合、試験時間内に「別のアプローチ」が見つかる保証はありません。
後者の場合、ゴリ押しのたくさんの計算、つまり「根性」では、どのくらい時間がかかるかわからない上、途中で計算ミスをする可能性が高まります。
ただ、どちらかを選ばなければ、制限時間に間に合いません。「チャレンジ」と「引き際」を常に天秤にかけているのです。
何かにこだわって足を止めてしまい、1問も正解できなかった、これが最悪の結果だからです。
企業もそうです。
ひとつのやり方にこだわり、時間や資産を際限なく投入して、失敗に終わった時にはもう取り返しがつかない、気がついたら会社が傾きかけていた、という例はよくあることです。
<<あわせて読みたい>>
「仮説思考」で生まれるリスクへの許容度
理系脳は、こうした結果になることを本能的に避けています。
そして彼らの問題への取り組み方には、「まず仮定から入る」特徴があります。
完全な逆算です。
自然科学と向き合うために必要なのは、「未知の現象」に対する基本姿勢です。
ビジネスを取り巻く環境もそうです。刻々と変化していきますし、先読みも簡単ではありません。常に「未知」に遭遇します。
その中で、「思わぬ結果」が伴うのは、ある種当然のことと考えた方が良いでしょう。
しかし、「仮説」を立ててまず手をつけなければ話を動かすことはできません。研究対象が刻々と変化する生き物であれば、なおさらのことです。
経験とデータから仮説を立て、まず進んでみるのです。
最初から完璧な手段は求めていません。
そして、因数分解にしろ、証明問題に向き合うにしろ、「大まかな法則」を当てはめ、それが正しければ話は短くて済む、そうでなければ違うアプローチを変えてみる、それでも説明がつかない部分は「誤差」として、存在するのが当然とすら考えています。
リスクありきで問題を俯瞰する上、リスクの計量化もしています。「誤差」であれば問題ないのです。
ドラッカーのいう「経営戦略とは何か」がピタリと当てはまります。
”経営戦略とは何か。それは、①リスクを伴う企業家的な意思決定を行い、②その実行に必要な活動を体系的に組織し、それらの活動の成果を期待したものと比較測定するという連続したプロセスである”
[1]_p39
それどころか、ドラッカーは
”経済的な活動とは、現在の資源を不確かな未来に投入することである。事実ではなく期待に投入することである。企業にとって、リスクは根源的なものであり、リスクを冒すことこそ基本的な機能である”
[1]_p174-175
とまで言い切っています。
「仮説と現実の違い」は、「新しい手段を学ぶためのチャンス」なのです。
結果が違えばすぐに新しい仮説を立て、実践するということの繰り返しです。これを何度繰り返しても苦になりません。
リスクに対しての許容度が高い上、むしろ「違い」にも何か法則性があるかもしれない、とポジティブ思考にすぐに切り替わります。
ところで、2020年1月、三菱UFJフィナンシャル・グループのCEOに史上初めて、理系出身の亀沢宏規氏が昇格すると発表され話題になりましたが、事程左様に、日本のトップマネジメントにはまだまだ、理系出身者が多くないのが実情です。
しかし、こんな思考回路を持つ理系出身者も、戦略やマーケティングに役立つ存在であるという仮説が証明できたと思われますが、いかがでしょうか。
<<あわせて読みたい>>
メタバースとは?メタバースの語源や意味、具体例をわかりやすく解説!
DXとは?なぜDXと略すの?デジタルトランスフォーメーションの意味や定義をわかりやすく解説
[1] 引用書籍:P.F.ドラッカー「エッセンシャル版マネジメント」(ダイヤモンド社)