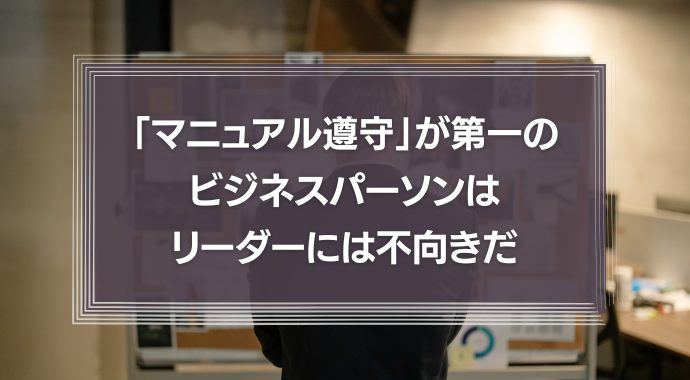今の時代、人生はそれぞれの価値観次第なので、マニュアルに従い正確にオペレーションを行うことに自分の価値を見出している人も、もちろんその価値観を否定されるものではない。
そしてそのような人も、会社組織の中では極めて重要な戦力であり、得難いビジネスパーソンである事実に変わりはないので、その前提で読み進めて頂きたい。
ではなぜ、「マニュアル遵守」が第一のビジネスパーソンは、リーダーには不向きなのか。
規則を遵守するビジネスパーソンではいけないのか。
以下、順を追って説明していきたい。
<<あわせて読みたい>>
『リーダーシップ』タイプ別6つの種類とそれぞれの特徴を徹底解説!
「外交的な人がリーダーに向いている?」実は内向型人間がリーダーにいた方が組織がうまく回る場合も
目次
成功体験から始まる組織の衰退
話を150年ほど巻き戻し、江戸から明治に時代が変わった頃の話から始めたい。
一足先に産業革命を成し遂げ、外洋に進出した欧米列強の進出。
それはついに「極東」である日本まで到達し、その外交圧力に国家のあり方まで影響を受けた結果、日本は1867年、250年以上に渡り続いた徳川の治世に終わりを告げ、明治維新という革命を経験した。
そして日本は、平成の今に続く基本的な国家の形、中央集権型の政治・経済の仕組みを作り、新しい国造りを急いだ。
しかし時代は、今とは全く価値観が異なる「力が正義」の時代だ。
強国は次々に他国を植民地化していき、弱い国は次々に列強の植民地として、その独立を奪われていく。
そんな中、日本にも明治維新から30余年の時を経て、いよいよ本格的に国が奪われる危機が訪れた。
それは、1904年に勃発した日露戦争だ。
当時のロシアの戦力は、全く比較にならないほどに日本を上回っていた、巨大軍事国家だ。
常備軍の数で、ロシアは日本の3倍にもなる巨大な兵力を有し、さらに武器の性能でも遥かに日本を上回る。
海軍力でも、同様に日本の3倍に相当する主力戦艦を揃えて、日本を圧倒していた。
当時はまだ、航空戦力は存在していない時代なので、これが全て。
つまり、日本はどうあがいてもまず勝つことができない戦争に打って出たことになる。
結論だけを言うと、日本はそれでも、この戦争に勝つことができた。
この際に日本の勝利を決定付けた戦いの一つが、「世界三大海戦」の一つに数えられる、日本海海戦だ。
この海戦では、日本の2倍に及ぶ主力戦艦を揃えたロシア太平洋艦隊を全滅させるなど、文字通り日本側が一方的な勝利を収めている。
そしてこの際、日本海軍の作戦を立案し、最高指揮官である連合艦隊司令長官の東郷平八郎をサポートしたのが、秋山真之・海軍中佐。
日本海軍の作戦立案を担う実務責任者だったが、秋山はこの期待に応え、日本だけでなく世界史に残るほどの結果を、残すことになる。
長い前ふりになってしまったが、お伝えしたいのはここからだ。
日露戦争が日本の勝利に終わった後、日本はその「奇跡の勝利」を教訓にまとめ、あるいは戦訓として、陸海軍の教育に取り入れることになる。
ある意味で、当たり前のことと言ってよいだろう。
あり得ないと思われていた勝利から得た教訓をまとめ、後世の知恵に活かそうと言う試みは、軍事組織ならずとも一般企業でも取り入れている手法だ。
できる人間のできるやり方をマニュアル化し、それを多くの社員でも再現できるよう、訓練を施す。
強い組織が例外なく繰り返してきた、必勝の方程式だ。
そしてこの日本海海戦で、大殊勲を挙げた秋山真之である。
当然のことながら、海軍内で大出世し、戦訓をまとめ作戦立案のマニュアルとも言うべき「海戦要務令」の編纂に取り組むことを命じられ、いかにして日本は勝利を得ることができたのか。
その基本的な考え方と、現場での応用までも含めた教訓をマニュアルとしてまとめ上げる大役を担うことになった。
極めて妥当な、強い組織のあるべき姿だ。
しかしここからが、大きな間違いの始まりであった。
「海戦要務令が聖典化している・・・」
この見出しは、「海戦要務令」をまとめ上げた秋山自身が後に、日本軍の滅亡を危惧し、警告した言葉だ。
秋山は、日本海海戦でいかにして勝利をもぎ取る作戦を立案することができたのか。
状況の変化に応じてどのように判断を変え、作戦を変更していったのか。
そのような教訓を「マニュアル化」し、海軍内での教育に活かすべく海戦要務令をまとめ上げたが、その主眼とするところは普遍的な原則の確認であり、決して戦訓の万能化ではなかった。
にも関わらず、ある意味でレジェンドと化していた作戦家ともいうべき秋山の著した戦訓は、その全てが絶対視されることになった。
いわば孫子の兵法のように、その考え方を諳(そら)んじることが優秀であるとされ、その戦い方はあらゆる局面で有効な、不磨の大典として聖典化されることになってしまったということだ。
だが言うまでもなく、あらゆる戦闘の局面で通用する必勝法など存在するはずがない。
存在するのは、マニュアルを基本としながら、それが今現在の環境や状況の中ではどう解釈するべきかというヒントのみだ。
実際にどう運用するのかは、その教訓を学んだ用兵者に委ねられており、そこからどのように普遍性を抜き出すかに過ぎない。
これをわかりやすく現代の会社経営の現場に置き換えてみれば、会社のマニュアルや規則などは、それが立案あるいは作成された時に、最適であると仮定された上での、いわば見本のようなものだ。
決して聖典化されるようなものではなく、極論すれば担当者もしくは責任者の、一過性の成功体験に過ぎない。
決して絶対視するようなものではない。
なお筆者はかつて、従業員850名ほどの中堅企業で副社長相当のNo.2を担っていたことがある。
株主には大手金融機関が名を連ねていたこともあり、求めに応じて様々な社内規則や運用マニュアルの作成も手掛けた。
加えて取引先の要望で、ISO向けのマニュアルも作成し、よく意味がわからない認証審査も経験している。
その上で言えることは、秋山真之のような歴史に名を残す大作戦家ですら、「自分の建てたマニュアルを聖典化する」という後進たちの愚行に、このままでは組織が確実にダメになると予告していたということだ。
ましてや筆者などのように、株主や取引先から要望され、やむを得ずマニュアルを整理し、その時の環境に応じた形をとりあえず書き上げてみた経験を持つものからすれば、会社の規則やマニュアルなど、しょせん叩き台に過ぎないことが嫌というほどわかっている。
決して、全知全能のエライ人が作ったものでも何でも無く、ステークホルダーのプレッシャーの中で、なんとか形にしたものであると言い換えてもいいだろう。
ここまで酷くはなくとも、きっと秋山真之・元海軍中将も様々なしがらみの中で、「海戦要務令」という組織のマニュアルを作成したはずだ。
それは、その時の環境や条件の中で作成されたものに過ぎず、決して聖典化されるべきものではない。
そのことを知り抜いていたからこそ、「海戦要務令が聖典化している」と、組織の将来を憂いていたのだろう。
「守・破・離」という考え方
このような考え方は、実は日本でも昔から、繰り返し教訓にまとめられ、また警告されてきた考え方だ。
おそらく最も古く、その考え方を文献に残したのは、千利休だろう。
言うまでもなく、茶の湯を大成した茶道の大家だが、利休はその人生の教訓をまとめた利休道歌の中で、以下のように歌っている。
「規矩作法(きくさほう) 守り尽くして破るとも 離るるとても本を忘るな」
ここから転じて、現代では武道や芸術の世界では、「守・破・離」という考え方が非常に大事にされる。
すなわち、物事の修行においては、最初は師匠の教えを守りその基本を大事にしろ。
そして次の段階では、その教えを守りながら自分の考え方や解釈に応じて、師匠の教えを破れ。
さらに最後には、師匠の教えから離れ、自分なりの世界観を作り上げろ、というものである。
しかし最後には、「本を忘るな」とあるように、教えを破り離れようとも、その本質だけは見失うな、と戒める。
これを企業経営にあてはめて解釈しても、やはりマニュアルなどはしょせん、改善のための叩き台に過ぎないと理解して差し支えないだろう。
もう一度言うが、会社に存在するルールなど、しょせん過去の成功体験を体系化したものに過ぎず、疑問を持たないほうがおかしいということである。
だからこそ、「マニュアル遵守」が第一のビジネスパーソンは、残念ながら使い物にならない。
少なくとも、組織を率いる覚悟があるビジネスパーソンにとって、規則やマニュアルなどは超えるべき壁であり、聖典などであるはずがないのだ。
<<あわせて読みたい>>
チームがおかしくなる原因は、大体において「リーダーの当たり前」と「部下の当たり前」が違うから。