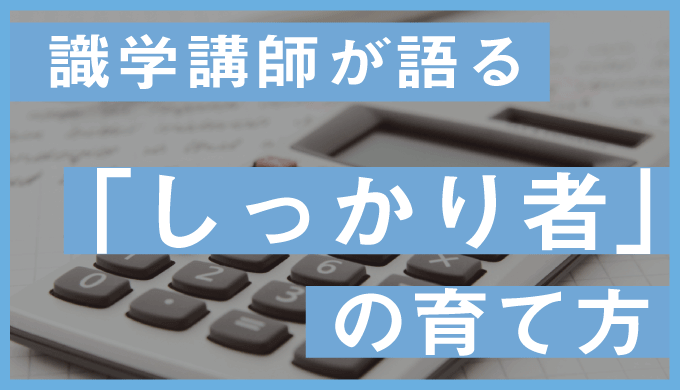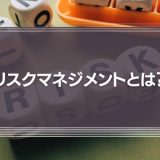貴社に評価制度はまだ必要ないと思っていませんか?
「まずは事業を軌道に載せたい」、「専門職のため、定量的な評価はできない」など、事業経営の中で、評価制度に対する優先順位は低いと思っていませんか?
しかし、「明確な評価」がない状態で、事業経営を続けるということは、ゴールのないマラソンを社員に強いるようなものです。明確な評価があるからこそ、社員は自分の不足に気づき、成長を実感できます。
では、「明確な評価」とは、何なのか。今回は、識学の視点から、3つのポイントで解説していきます。
目次
ポイント①:評価制度が必要なワケ
評価制度は、組織の維持継続のために必ず必要なものです。「明確な評価」について解説する前に、評価制度がない、または明確ではないとどうなってしまうのか、を解説していきます。
評価が明確ではないと、どうすれば評価を獲得できるのか、部下は「自分なりに考えて行動する」ことになります。
「自分なりに考えて動く」というのは、一見すると良いことに思えます。しかし、部下が自分なりに動いた結果として、あなたが期待したほどの成果が上がらなかった場合、部下の「自分なり」に対して良い評価をつけることができるでしょうか。
また、下された評価に部下は納得できるでしょうか。「後出しじゃんけん」と言われても、それまでです。
ここに「いつまでに、どうなっていたらいいのか」という基準があれば、このような事は起こりません。その基準を示すものが評価制度です。
よって、組織の大小や、事業内容等にかかわらず、組織として動く以上、評価制度は必要なのです。
ポイント②: 評価者は常に一人
「明確な評価」を可能にするステップの1つ目が、「評価者を常に一人にする」ということです。
多くの評価制度では、「自己評価」「一次評価者」「二次評価者」という設定がされています。この設定が、組織が機能不全を起こす原因になっています。
まず、自己評価は不要です。なぜなら、自己評価は、他者にとって有益な情報ではないからです。
例えば、ある企業が、「当社のサービスは日本一」という自己評価を発信したとしても、他者は有益な情報とは感じないでしょう。信憑性に欠ける感覚的な情報だからです。
これは会社内でも同じです。部下の自己評価を最終評価に入れることは、誤った評価を下すリスクを高めてしまいます。
また、評価者が複数いると、部下は「誰の評価を獲得すれば良いのか」迷ってしまい、集中力が下がります。
よって、評価者は常に一人である必要があるのです。そして、それは、直属の上司一人のみです。
ポイント③:評価項目の定量化
直属の上司一人が評価し、評価が確定する。
「そんなことをしたら、評価者の一存で評価が決まるので、評価が難しくなったり、評価に不満が生まれたりしてしまうではないか」と思っていませんか?
しかし、問題なのは、評価者が一人であることではなく、「評価項目が曖昧」なことです。
評価項目が曖昧なものになっているからこそ、恣意的な評価になったり、評価者によって評価がズレたりするのです。
すべての評価は定量化できる
では、評価項目は、どのように定義するべきでしょうか。それは「定量化」することです。
「そんなことは分かっている。定量化できないから困っているのだ」と思われるかもしれません。
しかし、実は、全ての評価は定義次第で定量化することができます。
例えば、「積極性」や「規律」を例に挙げてみます。
「積極性」があるかどうかは見る人によって違います。Aさんの評価を直属の上司が行う場合、前任の上司①はAさんの積極性を100点満点で70点と判断したが、現任の上司②はAさんの積極性を50点と評価する。
この場合、Aさんは今後どうすれば、自分の評価を獲得していけるのか、正しく認識することができません。
しかし、「積極性があると、どのような点で差が出るか」、は定量的に測ることができます。
例えば、貴社において、積極的に業務に取り組んでいると、時間当たり生産性が向上する。といえるのであれば、
「残業時間○○時間以内」や
「平均タスク消化○○件/作業1時間」
という定義で積極性を測ることができます。
このような定義を行えば、上司が変わることで評価が変わったり、どこを改善すれば高い評価が得られるのかわからなくなったり、ということは起こりません。
上司に求められる基準を達成するために、どうすれば時間当たり生産性の向上につながるのか、を部下が考えるようになります。
それが、積極性の向上につながるということになります。
さいごに
あなたが、部下に求めるのはどんなことでしょうか。また、それは正しく伝わっていますでしょうか?
部下が迷わずに仕事に取組み、成長を実感できる環境は、明確な評価制度により確保することができます。
実際にどんな評価項目を設定すればよいのか、どのように評価制度を運用していけばよいのか。少しでもご興味がありましたら、一度識学のコンサルタントにご相談ください。