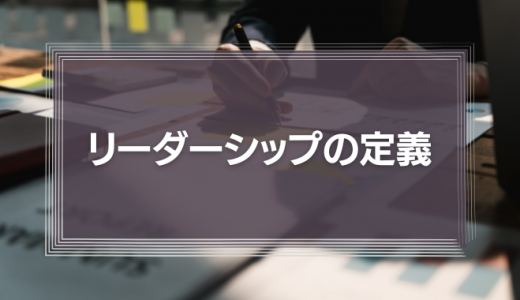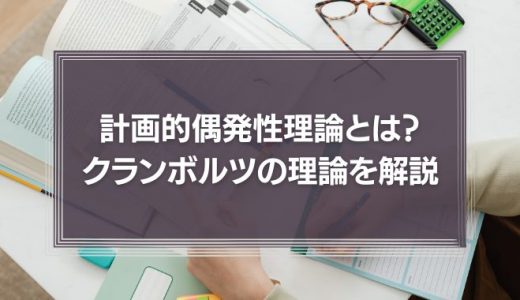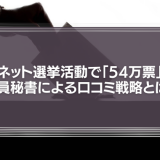目次
「上善(じょうぜん)は水のごとし」
中国古典の『老子(ろうし)』に、「上善(じょうぜん)は水のごとし」という有名な言葉があります。「上善如水」という吟醸酒の名前の由来であり、日本酒好きな方には、おなじみかもしれません。
老子の原文では、「上善は、水の若(ごと)し」となっており、四字熟語にする場合は、「上善若水(じゃくすい)」とするのが正式です。
しかし、豊臣秀吉の参謀であった戦国武将の黒田官兵衛(かんべい)が、『老子』の名言にちなんで、「如水(じょすい)」と号したこともあり、「上善如水」という言い方も普通になっています。(「如し」と「若し」は、どちらも同じような意味です。)
『老子』は、二千年も前に古代中国で書かれた古典ですが、東洋的な「サーバントリーダーシップ」の心得を説いていると読むこともできます。
「サーバントリーダシップ」とは、21世紀になって、日本でも注目されているリーダシップ理論です。「日本サーバント・リーダーシップ協会」のHPには、次のように解説されています。
「支配型リーダーシップの反対が、サーバントリーダーシップです。
サーバントリーダーシップは、ロバート・グリーンリーフ(1904~1990)が1970年に提唱した「リーダーである人は、まず相手に奉仕し、その後相手を導くものである」というリーダーシップ哲学です。
サーバントリーダーは、奉仕や支援を通じて、周囲から信頼を得て、主体的に協力してもらえる状況を作り出します。」
それに対して、『老子』は、どのように説いているのでしょうか。
せっかくですので、書き下し文と現代語訳を紹介いたしましょう。
『老子』第八章
<書き下し文>
「上善(じょうぜん)は水の若(ごと)し。
水は善(よ)く万物(ばんぶつ)を利(り)して争(あらそ)わず。
衆人(しゅうじん)の悪(にく)む所(ところ)に処(お)る。
故(ゆえ)に道(みち)に幾(ちか)し。(中略)
それ唯(た)だ争(あらそ)わず、故(ゆえ)に尤(とが)め無し」
<現代語訳>
「最上の善とは、たとえてみると、水のようなものである。
水は万物に利益を与えていながら、円(まる)い器に入れば円くなり、
四角な器に入れば四角になるといったように、決して他と争わない。
そして、多くの人々のいやがる低い位置に身を置く。
だから、水こそ「人の道(みち)」に近い存在といえる。(中略)
水のように争わないでおれば、他からうらみをかわず、
間違いがおこらないものだ。」
1977年、当時の福田赳夫総理に対して、安岡正篤先生は、『老子』の「上善は水のごとし」について、次のように解説しました。
「水は低い方に流れ、万物を活かし公平に潤します。
きらびやかに人前に出るよりも、人目を避け、縁の下の力持ちです。
だから『道』に近いといえます。
自己を捧げて他を活かすから上善でもあります。
政治家も自己を捧げて国家国民を潤し発展させてこそ、
真のステーツマンといえましょう。」
(『宰相の指導者 哲人安岡正篤の世界』神渡良平・講談社+α文庫、P94より)
総理大臣に対するアドバイスですので、政治の話になっていますが、最後の部分を「経営者や管理職は、自己を捧げて会社や部下を潤し、会社やチームを発展させてこそ、真のリーダーといえる」と読み替えれば、そのまま「サーバントリーダーシップ」の解説になっています。
トップダウン型のリーダーシップが普通である欧米に比べて、日本では、従来から「サーバントリーダーシップ」を発揮してきた経営者や管理職がいたように思います。
私が見た実例をご紹介しましょう。「サーバントリーダシップ」という概念や言葉が知られていなかった1990年代の話です。
<<あわせて読みたい>>
傍流の子会社から本社の総務部長に抜擢されたT氏
M社は、強烈な個性とアイディアの持ち主である創業者の下で、急成長したメーカーでした。年商が500億円を超え、社員も千人を超える規模にまで発展し、いよいよ株式上場を目指すことになりました。
株式を新規に上場するためには、業績も大事ですが、それと同じくらい会社の管理体制が整備されていることが求められます。これは、主幹事証券会社や証券取引所によって厳しく審査されるので、いい加減にごまかすことはできません。
通常、急成長したベンチャー企業は、営業部門や製造開発部門は強いのですが、管理部門は弱体であることが普通です。そのため、株式上場を決意してから、上場企業にふさわしい管理体制を整備することになります。
社員数が数十人の規模であれば、管理体制の整備も比較的容易ですが、千人規模となると、上場審査に耐える管理体制を整備するのに数年かかるのが普通です。
M社でも、主幹事証券や監査法人のコンサルティングを受けながら、管理体制の整備に取り組み始めました。しかし、困ったことに、社内に管理部門のリーダーとなる人材がいなかったのです。
非上場のうちは、経理や総務なども外注することが可能です。予算管理にしても、人事にしても、かなりアバウトでやって来られました。しかし、株式を上場するとなると、格段にレベルの高い管理体制を要求されますので、外注で済ますわけにはいきません。
M社では、経理部長に、メインバンクである大手都市銀行から支店長経験者を迎え入れました。その下の経理課長には、税理士資格を持っている人材を外部からスカウトして、若手社員を育てることにしました。
経理の場合は、業種や会社の規模が異なっても、基本形は共通することが多いので、銀行支店長経験者と税理士資格をもつ人材によって、軌道に乗りました。
しかし、困ったのは、総務部長の人選です。M社の場合、総務部は、経理以外の管理部門の仕事をすべて担当する体制になっていました。人事や経営企画、法務(契約管理)、広報など実に多様な仕事を引き受ける部署です。
総務部は、経営陣も含めた社内のすべての部署と関係を持つ唯一の部署です。常に社内全体を見渡し、疎遠になりがちな経営陣と現場や、縦割りになりがちな部署と部署を横断的につないで、社内をまとめる必要があります。
特に、M社の場合は、経営陣の目指す株式上場に向けて、上場企業に相応しい組織や業務フローにするため、既存のやり方を抜本的に見直す必要があり、その組織改革の要となるのが、総務部でした。
そのため、社内の各部署と緊密なコミュニケーションを取れる人材が総務部長になることが必要で、社歴が長く社員も多いM社の場合、外部からスカウトすることが難しい役職でした。
上場準備が始まるまで、管理部門を軽視してきたM社には、総務部長にふさわしい経験値のある人材がいないように見えました。そのとき、オーナー社長が総務部長に抜擢したのが、T氏でした。
T氏は、M社の物流子会社の部長をやっていた人物です。営業や製造開発という花形部門ではなく、傍流の倉庫部門を担当し、苦労して物流子会社を立ち上げた人でした。在職歴は長いので、社内で知らない人はいないのですが、およそ、切れ者ではなく、口下手。ですが、実直で誠実な人柄で知られていました。能力よりも人柄で評価されるタイプの人です。
子会社である程度の経験は積んでいるとはいえ、上場企業レベルの総務の仕事は、まったく未経験で、最初は、主幹事証券も、監査法人も、「T氏が総務部長では心もとない」という低い評価でした。
しかし、T氏は立派に期待に応え、M社の株式上場を成功させたのでした。
T氏の大きな長所は、知ったかぶりをしないことです。「自分は、上場企業の総務部のことは何も知らない」と自認し、何か問題があると、主幹事証券や監査法人やその他のコンサルタントに助言を仰ぎ、すなおに取り入れるようにしていました。
また、総務部に集められた若手の部下を励まし、彼らに存分に仕事をさせるように気を配っていました。特に、部下が失策を犯したときには、T氏は部下を責めず、部下をかばって、自分が気性の激しいオーナー社長の叱られ役になりました。
これは、部下の士気を大いに高めました。もともと、総務部には、有能な若手社員を集めていたこともあり、T氏の下で、みるみる総務部として機能するようになりました。
<<あわせて読みたい>>
常務からついに社長に就任
数年後に株式上場に成功する頃には、T氏は、押しも押されもしない名総務部長として知られるようになり、ほどなくして、管理部門を統括する常務に昇進しました。物流子会社に出向していた人材が本社の常務になるのは、M社では異例のことでした。
常務になっても、T氏の腰の低さは変わりません。何か問題が起きると、弁護士や会計士など社外の専門家に対して、「自分は物をしらないので困っています。ぜひ、良い知恵を教えてください。」といって有益なアドバイスを引き出し、それを部下に実行させていました。
さらに数年たって、オーナー社長が会長に退く時、後継社長に指名したのは、何とT常務でした。M社の本流である営業部門や製造開発部門からは、T氏よりも先に取締役になっていた専務が複数いたのですが、その人たちを飛び越して、T氏が社長に就任したのでした。
これには、さすがに周囲もビックリしました。何より、本人が一番驚いていました。「自分は社長の器ではないし、社長になりたいわけでもない。指名されて本当に困っている。ああ、困った」と親しい人にこぼしていたほどです。
創業者の意図は、おそらく、会長になっても、しばらくは院政を敷いて、営業や製造部門から本当に社長に相応しい人材が育つのを待つということだったのでしょう。そのためのつなぎ人事だったと思われます。
しかし、常に謙虚で、いばることのないT氏は、社長に就任しても、その姿勢を崩さず、先任の役員や有能な部課長の意見を活かし、うまく行かないことがあると、社長自ら、創業会長の叱られ役をこなして、オーナー会長の目指す方向に会社を導いていきました。
T氏が社長を担ったのは、2期4年間ですが、その間、会社の業績も好調で、不思議と社内がうまく治まりました。個性の強烈なオーナー会長の下で、目立たない社長でしたが、名経営者といってよい業績を上げて、無事に後任のエース役員に社長を引き継ぎました。
T氏は、「サーバントリーダーシップ」という言葉を知らなかったと思います。しかし、人格者であったT氏は、常に周囲を立てて、自分で叱られ役を担い、若手を育てることで、立派にサーバントリーダーの役割を果たしました。
T氏を見ていると、リーダーシップは、最終的に、人格の問題ではないかと思えてきます。中国古典では、リーダーシップを人格の問題と捉えて、人間性を磨くことを重視しています。
マネジメントスキルはとても大事ですが、すべての根底にある「人間性」や「人格」を磨くために、古典の知恵から学ぶこともまた大切ではないか思います。
以 上
<<あわせて読みたい>>