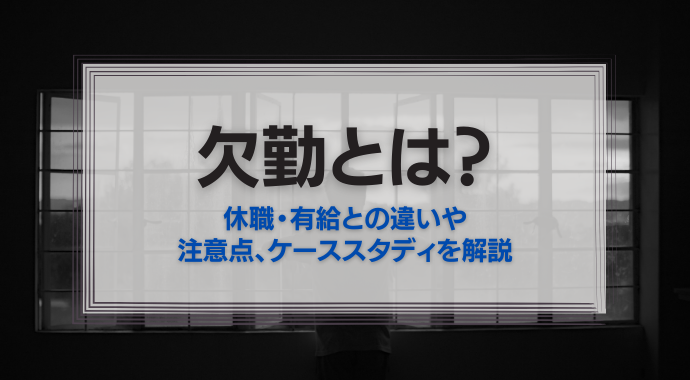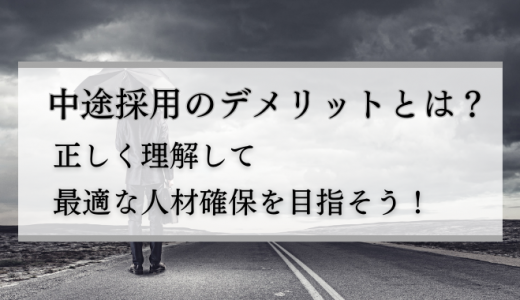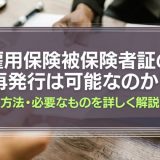従業員が仕事を休む手段として、休職、有給休暇、欠勤など、様々な選択肢が挙げられます。
そして、その選択肢によって企業の対応も変動します。そのため勤怠管理の担当者は、休職や欠勤などの違いを抑えておく必要があります。
そして中でも「欠勤」は、従業員にとっても企業にとっても、可能な限り避けるべき休みの取り方だと言えるでしょう。
本記事では、欠勤をメインテーマに、休業や休職との違いや、欠勤に関する注意点について解説していきます。
勤怠管理の担当者やマネージャーの方は、ぜひ最後まで読んでみてください。
目次
欠勤とは?【労働者の都合で休むこと】
有給休暇とは異なり、欠勤は労働基準法で明確に定められているわけではありません。
そして一般的に「欠勤」は、従業員が何かしらの理由で出勤日を休むことを指します。
欠勤する理由としては体調不良、私事、家族関連のトラブル、サボりなどが考えられますが、いずれも「労働者都合」であることがポイントです。
欠勤は、労働基準法で定められていないため、各企業の就業規則で定義されることが多いようです。
休業との違い
休業は、会社側もしくは労働者側の何かしらの事情で発生する休みのことを指します。
会社側の事情の具体例としては、業績悪化、機材トラブル、大規模な震災などが挙げられるでしょう。
また、労働者側の事情としては、通勤中・業務中の怪我などが挙げられます。
欠勤は労働者の自己都合によって発生するのに対して、休業はやむをえない事情によって発生するのが大きな違いです。
なお、労働基準法26条では「会社都合で労働者を休業させた場合に、労働者の最低限の生活を保障するために、使用者は平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければならない」とされています。
これを「休業手当」と言います。
休職との違い
休職は、労働者側の都合による長期的な休みのことを指します。
具体例としては、介護・育児、体調不良、語学留学などが挙げられるでしょう。
欠勤と休職の違いとしては、勤務時間を逸脱しているかどうかが挙げられます。
欠勤は労働者都合で勤務時間を逸脱しているのに対し、休職は労働者が企業に対してあらかじめ休職を申請しているので、勤務時間を逸脱しているわけではありません。
また、欠勤は一般的に「1日」や「数日程度」なのに対し、休職は「1ヶ月以上」になる場合が多いです。
なお、休業とは異なり、休職では最低限の賃金が法的に保障されません。なぜなら休職は、労働者都合による休業だからです。
ただし近年は、育児休職の支援を就業規則に盛り込む企業が増えている印象を受けます。
有給休暇との違い
年次有給休暇は、労働基準法39条で定められている労働者の権利で、給料が発生する休暇のことを指します。
①雇入れ日から6ヶ月以上経過していること、②全労働日の8割以上出勤していることの2つの条件を満たせば、労働者には年次有給休暇の権利が与えられます。
欠勤との最大の違いは、給料の有無です。
有給休暇を取得して休んだ場合は、その日分の給料が発生するのに対して、欠勤した日は基本的に給料が発生しません。
また、一般的に年次有給休暇は、原則として事前申請が必要です。
公休との違い
公休は、会社が定めた休日のことを指します。
労働基準法35条で法定休日が定められていますが、それに会社が定めた所定休日をあわせたものが公休です。
土日休みや祝日、年末年始、お盆休みなども公休に含まれます。
欠勤が労働者都合による休みなのに対して、公休は企業によってあらかじめ定められた休日である点が違いです。
欠勤控除とは?【ノーワーク・ノーペイの法則】
欠勤控除は、ノーワーク・ノーペイの法則に基づいて、欠勤した日の給料を控除することを指します。
「ノーワーク・ノーペイの法則」とは「働いていないのであれば給料は発生しない」とする考え方のことです。
労働基準法でも「労働者都合による欠勤分の賃金を保障せよ」といったことは特に述べられていません。
そのため、欠勤控除は労働基準法の違反にならないと考えられます。
欠勤控除になるケースとならないケース
欠勤控除になるケースは、労働者都合による欠勤で、かつ欠勤時に年次有給休暇を取得しなかった場合です。
この場合、その日の給与の支払い義務はありません。
なお、欠勤控除にならないケースとしては以下が挙げられます。
- 年次有給休暇を取得していた場合
- 欠勤した後に年次有給休暇の取得を認めた場合
- 会社都合による休業
- 会社独自の休暇制度を用いて休んだ場合
特に重要なのは「欠勤した後に年次有給休暇の取得を認めた場合」です。
例えば、体調不良などのやむを得ない事情で、突如欠勤になってしまった場合、後日、該当日ぶんの年次有給休暇を申請することで、欠勤を有給休暇に差し替えることができます。
多くの企業で、年次有給休暇の後日取得が認められているため、年次有給休暇が余った状態で欠勤した場合には、欠勤日を有給に差し替えることがほとんどだと思われます。
逆に、年次有給休暇を全て使い切った状態で欠勤してしまうと、問答無用で欠勤控除になる可能性があるので注意が必要です。
欠勤控除は法律で定められているわけではない
欠勤控除やノーワーク・ノーペイの法則は、労働基準法で定められているわけではありません。
あくまでも「従業員が欠勤したから、企業の賃金支払義務が免除される」というだけです。
そのため、欠勤控除については就業規則や給与規定に明記するのが一般的です。
欠勤控除が適用されるケースなどをあらかじめ明文化して、トラブルを避けるようにしましょう。
欠勤控除の計算方法の具体例
欠勤控除の計算方法は、会社によって異なるものの「月給額から欠勤分を算出する」のが一般的です。
計算式は以下の通りです。
欠勤控除額=月給額÷月の所定労働日数×欠勤日数
また、遅刻や早退したときの欠勤控除は1分単位で計算します。
計算式は以下の通りです。
欠勤控除額=月給額÷月の所定労働時間数×欠勤時間数
【従業員向け】欠勤に関する4つの注意点
ここでは従業員向けに欠勤に関する注意点を紹介していきます。
注意点は以下の通りです。
- 無断欠勤は絶対に避ける
- 前日までに欠勤届を提出しておく
- 有給休暇は自動申請ではない
- 欠勤理由を明確にする
それぞれ詳しく解説していきます。
注意点①:無断欠勤は絶対に避ける
まず従業員は、無断欠勤だけは絶対に避けるようにしましょう。
企業と労働者は雇用契約を結んでいるため、何も連絡しない無断欠勤は、雇用契約の違反になり、厳しい処罰を科される可能性があります。
どうしても欠勤せざるを得ない場合は、あらかじめ上司などに連絡するようにしましょう。
もちろん、連絡は早ければ早いほど良いです。
注意点②:前日までに欠勤届を提出しておく
やむを得ず欠勤する場合は、前日までに欠勤届を提出しておくようにしましょう。
従業員が1人でも欠勤してしまうことで、そのしわ寄せが同僚に行ってしまうためです。
あらかじめ欠勤届を出しておけば、上司が欠勤分の業務を他メンバーに分散させるなど、事前に対処することができます。
そしてできれば、欠勤する当人が、当日分の業務の割り振りや引き継ぎを実施した方がいいでしょう。
注意点③:有給休暇は自動申請ではない
有給が自動申請ではない点には注意が必要です。
企業によっては、欠勤した日の後日での有給休暇取得を認めるケースがあります。
労働基準法上では、有給休暇の取得は事前申請が原則であるものの、裁判例を見るに、有給休暇の事後申請の可否は企業に任されているようです。
そのため企業としては、従業員が欠勤した場合の選択肢として「そのまま欠勤扱いにする」か「有給休暇の事後申請を認める」の2つの選択肢があります。
企業が勝手に有給休暇を自動適用してくれるわけではありません。
だからこそ従業員は、欠勤した日を有給休暇としたい場合は、自ら取得申請する必要があります。
注意点④:欠勤理由を明確に説明する
欠勤する場合は、可能な限り欠勤理由を明確に説明した方がいいでしょう。
基本的に欠勤は、雇用契約に違反した行為です。
欠勤したことがやむを得ない理由であったことを説明できなければ、企業側も納得できないでしょう。
また、体調不良に関しては、診療明細書を医療機関に発行してもらうのがベターな選択です。
【事業者向け】欠勤に関する3つの注意点
ここからは事業者向けの注意点を解説していきます。
注意点は以下の通りです。
- 労働分の給料の支払い義務はある
- 欠勤に関する取り決めは社内規則で明確にする
- 給料支払いの形態を確認しておく
それぞれ詳しく解説していきます。
注意点①:労働分の給料の支払い義務はある
従業員がどれだけ欠勤しようと、企業には労働分の給料の支払い義務が発生する点には注意が必要です。
例えば、月の所定労働日数が20日だとして、そのうち19日で無断欠勤されたとします。
企業の秩序を乱すあるまじき行為です。しかし、だからといって、給与を支払わないわけにはいきません。
19日無断欠勤されたとしても、1日は出勤しているため、企業は1日分の給料を支払う必要があります。
なお、あまりにも無断欠勤が続いているなど、適切な理由があれば、企業は労働者に対して減給処分を下すことが可能です。
ただし減給額は、労働基準法91条で「1回の額が平均賃金の1日分の半分を超えてはならず、総額は一賃金支払期における賃金(月給)の10%以下」と定められているので、注意が必要です。
注意点②:欠勤に関する取り決めは社内規則で明確にする
欠勤に関する取り決めは、社内規則であらかじめ明確にしておくのがいいでしょう。
欠勤控除や年次有給休暇関連の問題は、たびたび発生するトラブルです。
欠勤控除の計算方法、有給休暇の事後申請の判断ラインなどをあらかじめ明確にしておいて、トラブルを避けましょう。
注意点③:給料支払いの形態を確認しておく
欠勤控除を適用する場合は、給料支払いの形態を確認しておくことが重要です。
一般的な企業では月給制が用いられる一方で、中には完全月給制が用いられている企業もあります。
完全月給制は、労働時間関係なしに、一定の月給が支払われる給与支払制度のことを指します。
完全月給制の場合は、たとえ遅刻、早退、終日欠勤があっても、欠勤控除を適用させることはできません。
また、業務委託契約において、労働時間ではなくプロジェクト単位で報酬を決定している場合も、欠勤控除できる可能性がかなり低いと言えます。
欠勤に関するケーススタディ
ここでは欠勤に関するケーススタディを紹介していきます。
無断欠勤を理由に従業員を解雇できる?
1度の無断欠勤で従業員を解雇することは、社会通念上できません。
一方で、何度も無断欠勤を繰り返したり、欠勤理由が曖昧だったりする場合で、かつ何度も話し合いしても改善が見込めない場合は、解雇予告が可能です。
ただし解雇予告は、少なくとも30日以上前に予告しなければならないことが労働基準法21条で定められています。
インフルエンザも欠勤になる?
一般的に、インフルエンザや新型コロナウイルスなどに感染した場合は出社を控えるべきです。
そのため、企業の定める年次有給休暇を取得して、対応した方がいいでしょう。
とはいえ「インフルエンザによる欠勤では絶対に有給を取得する」というルールが、労働基準法で定められているわけではありません。
また、有給休暇の残り日数が無ければ、やはり欠勤として取り扱われてしまいます。
いずれにせよ、インフルエンザなどの感染症で欠勤した場合の対応については、企業の就業規則を確認した方がいいでしょう。
欠勤は代休や残業と相殺できる?
欠勤を代休や残業と相殺することは、原則としては認められていません。
ただし、労働者と使用者との間で同意を得ている場合は可能です。
一方で、企業による一方的な相殺は、労働基準法の違反になる可能性が極めて高いと言えます。
また、あまりにも労働時間が変則的になりすぎると、労働時間管理の透明性が損なわれる可能性があるので、注意が必要です。
まとめ
それでは本記事をまとめていきます。
- 欠勤は、従業員が何かしらの理由で出勤日を休むこと
- 企業は、欠勤日の給与を支払う必要はない
- 欠勤に関する取り決めは就業規則で明確にした方がいい
欠勤に関するルールは、あらかじめ就業規則で明確にしておくのが無難です。
また、労働基準法を上書きするようなルールを就業規則で設ける場合は、労働者に有利な形にする必要があります。
有給の事後申請や、感染症に対する企業独自の有給休暇制度が、その典型例です。
どちらにせよ、欠勤に関するルールは、あらかじめ明確にしておいた方がいいでしょう。