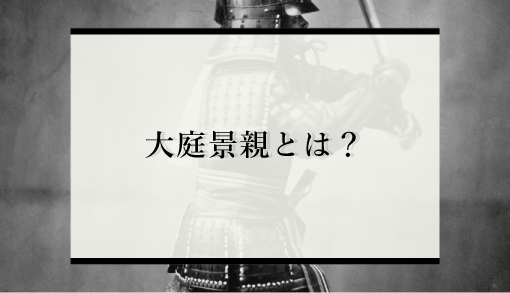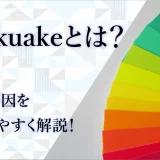- 「会社を支えるのは人だ。人を大切にせずして、何をしようというのか」
- 「金は儲けたいが、信用を落としてまで金を儲けることはできない」
- 「僕は景気のいい時に、景気の悪い時のことを考えて準備しておけと言っている」
上記の言葉はどれも出光佐三(いでみつ さぞう)のもので、彼の人物像がよく表れています。
出光佐三は「出光興産」の創業者であり、百田尚樹氏が書いた歴史経済小説『海賊とよばれた男』の主人公のモデルとなった人物です。
「石油王」とも呼ばれた出光佐三は武士道的経営を貫きました。お金や権力のために事業をするのではなく、「人間尊重主義」と「大家族主義」を重要視して会社を存続させていったのです。
出光興産のことは知っていても、その創業者の偉大な功績について知っている人は少ないのではないでしょうか?本記事ではそんな出光佐三の人生や、人物像がわかる逸話・エピソードなどを紹介していきます。
目次
出光佐三の生い立ち
出光佐三は明治18年(1885年)、藍玉を仕入れて販売する藍問屋の父、出光藤六と母・千代の次男として福岡県に生まれました。
出光佐三は生まれた頃から体が弱く神経症を患っていました。また、本も読めないほど目が悪く、読めたとしても読書をする忍耐力も無かったといいます。しかし、そうしたハンデを「物事を徹底的に考え抜くこと」で乗り切ることを学びました。
そのおかげで、中学校を上から3番目の成績で卒業することができました。そして、現在の神戸大学である神戸高等商業学校に進学します。
「人間尊重主義」のルーツとなる人物との出会い
出光佐三が経営において大事にしていたことの一つに「人間尊重主義」があります。
このルーツとなった人物とは神戸高等商業学校で出会いました。それが、校長の水島銕也です。当時、拝金主義がもてはやされていた時代のなかで、水島銕也校長からは「黄金の奴隷になるな」と教わりました。
水島銕也校長は、国家のためになる事業をするべきだと教えており、これが出光佐三の「人間尊重主義」や「士魂商才(武士道的経営)」につながることになるのです。
小さなお店で丁稚奉公をする
明治42年(1909年)に神戸高等商業学校を卒業した出光佐三は、石油や機械油、小麦粉を扱う酒井商店という従業員が3人しかいないお店で丁稚奉公をするようになります。
そんな小さい会社に入った出光佐三を見て、同級生たちは「あいつは大学の面汚しだ」と批判しました。なぜなら、出光佐三がいた神戸高等商業学校はエリート校であり、卒業生が入社する会社としてふさわしくないと考えたからです。
なぜ出光佐三は小さい酒井商店を選んだのでしょうか?
酒井商店を選んだ理由
大企業に入社すれば仕事の一部しか担当できませんが、小さい酒井商店であれば主人がどのように仕事をしているのか、全てを間近で見ることができます。
出光佐三は誰よりも早く仕事を始め、誰よりも遅くまで仕事をしている主人の姿から全てを学びたいと考えていたのです。また、徹底的に考え抜くことが習慣化していた出光佐三のことなので、エネルギー源の中心が石炭から石油へ転換していくことも考えていたのでしょう。
25歳で出光商会を設立
酒井商店で丁稚奉公をしていた出光佐三は、ある時から独立を考えるようになります。その理由は、父親が営んでいた事業がうまくいかなくなってきたからです。
早く独立して家族を助けたいものの、開業するために必要な資金を調達できず、もちろん銀行もお金を貸してはくれません。
悩み続けた出光佐三に救いの手を差し伸べたのが、資産家の日田重太郎(ひた じゅうたろう)です。出光佐三は学生時代、日田重太郎の息子の家庭教師をしていました。
そのとき日田重太郎は、神社仏閣を巡拝することが趣味だった出光佐三の純粋さを見て、佐三のことがすっかり気に入ってしまったのです。
6,000万円もの大金を無条件で出した日田重太郎
そんな縁もあり、日田重太郎は独立を考えている出光佐三に対して「独立するための資金がなくて悩んでいるんじゃないのかね」と声をかけます。そして、さらにこう続けました。「京都の家を売却しておよそ6,000円余るから、君にあげよう」。
出光佐三は驚きました。なぜなら当時の6,000円は、現在の価値で換算すると6,000万円にもなるからです。ただ、さらに驚くべきことは日田重太郎が提示した条件でした。それは下記のようなものです。
- このお金は返す必要はなく、このお金を日田重太郎が出したことは他言しないこと
- 働く人を家族と考えて良好な関係を築き上げること
- 自分の考えを絶対に曲げず貫き通すこと
出光佐三は、このお金をもとに出光商会を設立。25歳で独立することになりました。
失敗続きの3年間を過ごす
独立し始めてからは機械油を扱っていましたが、当時は電気モーターへの切り替えが進んでいたため、機械油の需要が無くなってきていました。さらに、賄賂を求める相手とは商売をしなかったため、日田重太郎からもらった資金は3年で使い切ってしまったのです。
廃業するしかないと考えた出光佐三は、日田重太郎にその報告をしに行きました。しかし、そんな出光佐三を見た日田重太郎はこう言います。
「3年でうまくいかないなら5年。5年でうまくいかないなら10年となぜ続けない。まだ売れる家は残っているから、その家を売却すればまた続けられるだろう」。
出光佐三はこの言葉を受けて、もうやるしかないと考えて覚悟を決めました。
「海賊」と呼ばれた理由
出光佐三は百田尚樹氏の歴史小説『海賊とよばれた男』の主人公である国岡鐡造のモデルになっていますが、なぜ出光佐三は「海賊」と呼ばれたのでしょうか? その秘密は、出光佐三の仕事のやり方にありました。
出光商会を設立したはじめの3年間は失敗するも、日田重太郎にさらなる資金提供を受けた出光佐三は方針転換をします。
それまで、運搬業者や漁民の船では価格が高い灯油を使用していましたが、安い軽油でも使えることを証明してコストカットを図り、利益を大幅にあげたのです。
また当時、軽油を売る際には陸上で一斗缶に軽油を移して売っていたため非常に効率が悪いやり方でした。そこで出光佐三は伝馬船(近世から近代にかけての日本で用いられた小型の船)に軽油タンクと計量装置を取り付けて、海上で漁船に直接給油できるようにしたのです。
好評を博した海上ガソリンスタンド
この海上ガソリンスタンドは評判を呼び、運搬船や漁船のほとんどが出光商会の客となり、下関や門司一帯を掌握してしまいました。しかし、ライバル企業の軽油卸店からは「海上は販売区域を超えている」と叩かれてしまいます。
それでも出光佐三は「境界線など存在しない」と反論し、海上ガソリンスタンドを続けました。これにより、軽油販売業者は出光佐三を敬遠し、自分たちの顧客を奪う「海賊」と呼んだのです。
出光佐三は商売は消費者のためになることが重要であると考えていたため、既得権益となっていた販売区域を忌避し、少しでも安い軽油を売るためにライバル企業の批判を受けながらも事業をやめなかったのです。
敗戦後でも一人もクビにせず約束を守る
昭和20年(1945年)、日本は大東亜戦争に敗れました。当時、従業員1,000人ほどを抱える大企業になっていた出光興産は資産の大半を失い、残ったのは借金と従業員だけでした。しかし、敗戦から2日後に出光佐三は従業員に向けて、下記の言葉を送りました。
「私は、この際、店員諸君に3つのことを申し上げます。
一、愚痴をやめよ
二、世界無比の三千年の歴史を見直せ
三、そして今から建設にかかれ
また、当時はさまざまな企業が当たり前のように従業員をクビにしていましたが、出光佐三は一人もクビにしないことを宣言しました。
これは「従業員は家族と考えること」という日田重太郎との約束であり、出光佐三の「人間尊重主義」でもあったのです。
GHQによる危険な指令を喜んでこなす
一人もクビにしないと決めた出光佐三は、農業や水産業、酢や醤油の販売、印刷業、ラジオの修理などありとあらゆる仕事をするようになりますが、どれも軌道に乗ることはありませんでした。
そんななか一つのチャンスが舞い込んできます。それはGHQ(占領軍本部)による指令で、戦時中の海軍が使用していた燃料タンクの底に残っていた油の回収作業でした。
燃料タンクの底にある油の回収作業は過酷な業務で、中毒や爆発、窒息のリスクがあり、誰もやりたがらないため、回り回って出光佐三のもとへ舞い込んできたのです。
出光佐三は「また石油業界で仕事ができる」と喜んでこの仕事を引き受けました。そして、従業員総出で仕事に取り組み、手足がただれながらも原油2万キロリットルの回収に成功したのです。
この仕事ぶりを見たGHQは出光を高く評価します。これが、出光興産にとって後の石油業界での仕事につながることになりました。
驚異的な行動力を示した「日章丸事件」
出光佐三を語る上で外せないのが、出光佐三の驚異的な行動力を象徴する「日章丸事件」です。
第二次世界大戦後の日本は、アメリカやイギリスに占領され、主権回復後も両国との同盟関係があるため、独自ルートで石油を自由に輸入できませんでした。そして、このことが経済発展の障害となっていたのです。
さらに、原油国のイランはイギリスの石油メジャー「アングロ・イラニアン社」と係争中でした。その理由は、イランの石油はアングロ・イラニアン社によって支配されており、イランがこれに対して石油の国有化を宣言したためです。
この状況に、イラン国民と日本経済の発展を憂慮した出光佐三は、石油市場を支配していた石油メジャーに喧嘩を売りました。
海上封鎖のなか極秘で石油を持ち帰ることに成功
イランの石油国有化への報復として、イギリスは艦隊を派遣し海上封鎖を行いました。これによりイランは石油を売ることができなくなり、出光佐三はイギリスの汚いやり方に憤慨します。
出光佐三は撃沈されるリスクを冒して、自社で保有していた大型タンカー日章丸を神戸港から極秘裏に出港させました。もちろん、国際法上の対策や法の抜け道を利用するための必要書類の作成、航海上の危険箇所の調査などの入念な準備をした上で、です。
航路を偽装するなどイギリス海軍に見つからないようにすることで、日章丸はイランに到着。そして石油を日本に持ち帰ることに成功しました。
この事件は、世界中で報道され国際的事件として知られることになりましたが、それと同時に出光佐三の驚異的な行動力を示す逸話としても有名になったのです。
自分の使命を全うした出光佐三
アングロ・イラニアン社から訴えられた出光佐三は、世界に向けて堂々とこう語りました。
「出光の利益のために石油を輸入したのではない。そのような小さな目的のために、50人の乗員の命と日章丸を危険に晒したのではない。横暴な国際石油カルテルの支配に対抗し、消費者に安い石油を提供するために輸入したのだ」
日本においても、当時世界第二位の海軍力を誇るイギリスに「喧嘩を売った事件」として大きく報道されました。
当然、イギリスは激怒しますが、イギリスによる石油独占をよく思っていなかったアメリカは黙認します。痛快な事件として認知された世論の後押しもあり、アングロ・イラニアン社は最終的に訴訟を引っ込めることになります。
出光佐三の驚くべき経営哲学
出光佐三は驚くべき経営を実践していました。
それは、「四無主義」というもので、
- タイムカードなし
- 出勤簿なし
- クビなし
- 定年なし
という、一般的な企業からすると「どうかしている」と言われるようなものです。
しかし、出光佐三からしてみれば「従業員は家族でありモノではない。したがって家族に定年もないし時間を管理する必要もない」と言います。
驚くべきは、従業員が数人や数十人の時だけではなく、従業員が数千人規模になっても四無主義を貫いていることです。
まとめ
ここまで出光佐三の人生や驚くべきエピソード、経営哲学を見てきました。
出光佐三は1981年に95歳で亡くなりますが、このとき長年側近を務めていた石田正實氏は、「出光佐三は一度も『金を儲けろ」とは言わなかった」と明かしています。
さらに、出光佐三が亡くなった際には、昭和天皇が「出光佐三、逝く」として和歌を詠んでいます。
従業員を一人もクビにせず、お金や権力のためではなく国や消費者のために事業を続けた出光佐三の生き様は、現代を生きる私たちにとって学ぶべき点が多いのではないでしょうか。