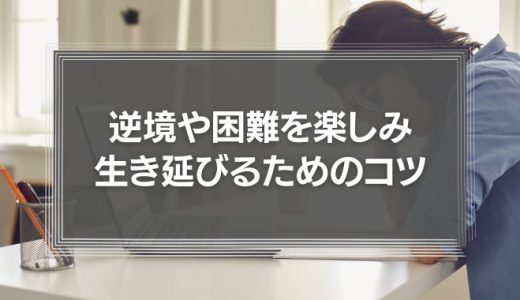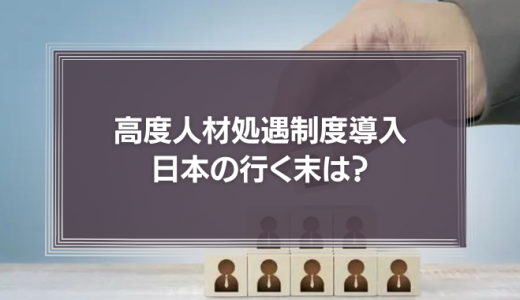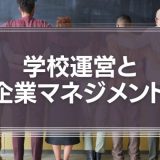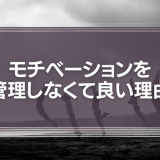早速の本題で恐縮だが、私は経営に失敗し、事業を売却したことがある。
当時の私の肩書きは、取締役経営企画室長兼CFO(最高財務責任者)。
事実上会社のNo.2 であり、銀行の推薦で、ある会社の経営再建を託されて送り込まれた外様役員だった。
そして、様々に手を尽くし経営再建を画策するも、最後には力及ばず、キャッシュが底をつくことが確定的になる。
追い込まれた私は、自分自身が大手証券会社出身ということもあり、この窮地を会社の主力事業を売却することで乗り切る計画を立てた。
いわば、東芝が虎の子である半導体事業を売却し、経営危機を乗り越えようとしたようなものだ。
もちろん数字の桁は一つどころではない桁違いの話だが、経営危機に臨む役員という意味では、おそらく同じ思いであろう。
断腸の思い、あるいは苦渋の決断という表現では言い表せないほどの複雑な感情で、「究極の撤退戦」に臨むことになった。
なおこの時、私がM&Aに取り組むことになった会社の規模は、従業員数で800名(パート・アルバイトを含む)ほどの大所帯だ。
売却を考えている事業部門は年商が50億円近くあり、年間の利益は経常利益ベースで1~1.5億円程度だったので、典型的な薄利事業。
しかし、もはや処分できる不動産や資産は全て換金し尽くしている。
主力事業を生き残らせるためには、株主と相談の上でもこの事業を売却するしか他に方法がないだろうという結論に達していた。
そして、M&A仲介専業の業界大手に依頼し、M&Aに臨むことになった。
目次
「M&Aは専任仲介が基本です」
証券会社にいた頃にも、何度かM&Aには直接・間接に携わっていたが、自分がディール(取引)の主体になるのは初めての経験だった。
そのため、経営トップとの連携ミスなど反省点も多いものとなったが、このM&Aに際しては最初からいきなり、大きな失敗をやらかしてしまうことになる。
それは「エクイティの取引では、専門家の言うことを真に受けるな」という大原則の認識に、すっかりと甘くなっていたことだ。
これはどんな専門家にも言えることだが、基本的に専門家は、クライアントの利益のためだけにその能力を発揮する。
有利な情報は十二分に活用するが、不利な情報は積極的に伝えるようなことはしない。
弁護士や公認会計士のような高度な知見が求められる専門家はもちろん、率直に言ってM&Aの仲介事業者のような「専門家」でも同様だ。
そして、さらに厄介なのは、クライアントの利益に繋がることであっても、業界のやり方や慣習を優先し、本当の意味でクライアント利益をファーストに考える専門家などほとんどいないという現実である。
なお、少し前提条件を先にお話しておくとM&Aを仲介する「専門家」は、よほど変わった報酬の仕組みを定めていない限り、売却側、買収側の双方から入る成功報酬を主な収益源としている。
最大手から中小の仲介事業者まで、その仕組みはほとんど変わらない。
そして成功報酬は、多くの場合、売り手と買い手の双方から、成立価格に同じ割合を掛けた金額を受け取る。
であれば、M&A仲介事業者にとっては売り手と買い手の双方がクライアントなので、中立の立場でディールを捌くと思われるかも知れない。
しかしそれは、大きな幻想であり過ちだ。
仲介事業者は多くの場合、買い手にとって有利なディールを成立させるよう交渉を誘導するベクトルが働く。
スモールディール(主に1億円以下の小さな案件)であればまた話が変わるが、数億円クラスの仲介の場合には、この傾向が特に顕著だ。
それはなぜか。
冷静に考えてみて欲しいのだが、会社や事業を売って目先の運転資金に換えるほど追い詰められている経営者が、この先再び、M&A仲介事業者のクライアントになることがあり得るだろうか。
売り物になるようなものを全て売り払い、最後に行き着いたM&Aなのだから、2度目の事業売却など通常は考えられない。
まして、奇跡的に事業が復活し、買収側としてクライアントになる確率など、おそらく天文学的な確率のレベルだろう。
つまり、一度きりの付き合いしか無い可能性が極めて高い“クライアント”ということだ。
一方で、数億円を越えるような事業の買収ができるような会社は概ねM&Aに意欲的であり、一度きりではなく何度も、条件の合う会社を買収する傾向が強い。
そしてそのような会社にはM&A仲介会社の担当者がついており、会社の意向に沿う売り物件を常にリサーチしている。
そして条件に合う会社を有利な条件で斡旋することで、その会社と担当者の評価は上がり、ますます頼りにされるようになる。
つまりM&Aの仲介事業者は、ディールの条件にもよるが決して中立ではなく、買い手有利なモティベーションで案件をまとめようとしている可能性を警戒しなくてはならないということだ。
そのような前提で、以下話を読み進めて頂きたい。
大手M&A仲介事業者は当社の意向を理解すると、早速1社の買収候補先を打診してきた。
ただし、実際に交渉を進める前に契約書を締結する必要がある。
そしてこの際、仲介事業者が提示した契約書には「専任仲介条項」が含まれていた。
専任仲介条項とは、M&Aの交渉が始まれば他の仲介会社とは一切の交渉を禁じる内容で、当然、他の会社と売却交渉をしないという意味の取り決めだ。
つまり、どうしても売らなければ会社が立ち行かなくなるという弱い立場の当社と、条件さえ合えば買ってやっても良いという買い手側が1対1で交渉のテーブルに付くことを意味する。
どう考えても、この取り決めはフェアではない内容だが、主にスモールM&Aの現場では当たり前に契約書に盛り込まれる条項だ。
必ずしも、売り手側に一方的に不利となる条項ではないものの、総じて買い手側を最初から有利にする意味合いが大きい。
「なぜこんな条件を呑まなければいけないのか。」
そう質問する私に、仲介事業者の担当者は「M&Aはそういうものです。」と答える。
そして「専門家」として、その必然は説明せずにこの内容でなければ仲介できないと突き放しにかかる。
結局この際、経営トップの強い意向もあり「専任仲介条項」を呑んだ上で最初のM&A交渉が始まることになった。
そしてそれからは、まさに悪夢のような交渉だ。
買収側は、当社の財務諸表や契約先、契約先ごとの単価や条件などの全てをDD(デューデリジェンス:事業内容の精査)で丸裸にしていく。
もはやノウハウも営業リストも全て、競合でもある同業他社にオープンにした上で、事業の値付けが始まるわけだ。
そして、「早く交渉をまとめないと、5ヶ月後には資金がショートするんですよね?」と言った具合で、揺さぶりをかける。
交渉相手が1社であるがゆえに、駆け引きなど全く通用しない。
ただ単に、買い手の品定めとディスカウント交渉のみであり、いわば戦争に敗れた敗者が、降伏条件を話し合っているようなものだ。
気に入らなければ交渉は打ち切るぞ?という態度をチラつかせれば、相手はいくらでも譲歩するという環境が完全に成立している。
そして長い時間を掛けて交渉をした挙げ句、買い手側は3億円ほどの、当時のM&A相場から考えて破格の安値を最後通告してきた。
そしてその金額では、とても会社の再建が立ち行かないことは目に見えていたので、ギリギリの判断で交渉を打ち切った。
結局、当社はただ単に破綻への砂時計だけが大きく進み、そして同業他社にノウハウや営業先リストなどの情報を全て吸い取られただけの結果となり、交渉は終了した。
「降りたければ降りて下さい」
その直後だ。
M&A仲介会社の担当者はすぐに飛んできて、要旨以下のようなことを言った。
「大変なことになりましたね。もう御社には余り時間は残されていないと思いますので、すぐに次の交渉を始めましょう。既に、次の買収候補相手は見つけてあります。」
そして差し出した契約書には、またしても「専任仲介条項」が盛り込まれている。
繰り返しになるがこれは、交渉相手を1社だけに制限する、被買収側から見れば品定めをされる事が前提の条文だ。
先の交渉でイラツイていた私は、その担当者に改めて聞いた。
「もう一度聞きますが、この専任仲介条項は外せないのですか?」
「外せません。M&Aとはそういうものです。専任仲介条項が呑めないのであれば、仲介はできません。」
実はこの時、別の株主系のM&A仲介事業者から、より有利なディール(取引)になる可能性がある交渉相手を、水面下で打診を受けていた。
そのため、どう考えてもM&Aはビット(入札)で行うべきだと考えていた私は、この、足元を見たような担当者の物言いにさらにイラッと来て、その場で言い放った。
「M&Aはビットで行うことにします。当社には他に、株主系の仲介事業者からも案件の持ち込みがきていますので、当然の選択です。降りたければ降りて下さい。」
これには担当者も大いに焦り、ブラフの可能性を疑って揺さぶりをかけるが、残念ながら裏表のない本当の話だ。
この状況で強気の私に、さすがにブラフではないことを悟った担当者は、一旦留保すると話し、会社に持ち帰る。
しかし程なくして、非常に悔しそうに「ビットに同意します」と伝えてきた。
ここで少し前提をお話すると、ビット(入札)とは、2社以上の買収希望企業による、買収条件の戦わせあいだ。
自社が、売り物になるような魅力的な事業を持っている場合には、当然のことながらM&Aは入札で行うべきである。
どうしても早く売りたいと焦っている売り手企業と、どうしても競合他社にこの会社(事業)を渡すわけにはいかないと考える買い手企業を同等の立場にするには、これしか方法がないことは明白だ。
記憶に新しいシャープの買収劇でも、日本の産業革新機構と台湾の鴻海精密工業が最後まで条件を戦わせあったことで、(売り手目線で)買収条件はどんどんと釣り上がっていった。
一般に、大きなM&Aはビットで行うことが常識だと言っても良いだろう。
そしてこのように、買い手側の負担が非常に大きくなる可能性が高いM&Aの形を仲介事業者が好まないのは、先にご説明したような事情がある。
できれば、買い手側の負担を抑えた形でディールを成立させることで、ご褒美(次の取引)を頂けるのだから当然だろう。
実際に私自身、このディールでは無理やりビットに契約書を書き換えさせた仲介事業者からは、相当な嫌がらせを受け続けた。
それはともかくとして、2度めの交渉だ。
買収を検討するに先立ち、DD(事業の精査)を受ける手順は全く変わらない。
しかし前回は、ただ単に会社のあら捜しをして、その全てがディスカウント要因として買収価額から引かれていく作業を指を加え見ていただけだったが、今度はそのリスクを「どこまで面倒を見るか」。
その交渉が始まるという変化を経験した。
具体的には、例えば長い間塩漬けになっている、回収の見込みが見通せない営業保証金などの債権だ。
交渉相手が1社の場合には、無条件で会社の価値から差し引かれていく。
しかしビットの場合、買収希望金額を引き下げ過ぎると負けることがわかっているので、
「この債権の回収可能性はどれくらいか」
という質問に変わり、
「できれば、回収を担保できる書面を、先方と取り交わして欲しい」
というように、「できる限り買収価額を下げない努力」をする方向にベクトルが変わる。
この変化は、非常に大きなものであった。
そして迎えた、ビットに参加した両社からの買収希望価格の提示。
1社は10億円を提示し、もう1社は6億円の最終提示となった。
この金額は、どちらも当社が再建に取り組める最低金額として設定した売却希望額をクリアするものであり、非常に満足の行く交渉になった。
私はCFOとして、最後の最後に少しはよいディールをまとめることができた。
専門家の言うことは、ただの判断材料という強い思いを
このディールでは、私は改めて「専門家」の言うことは判断材料の一つに過ぎないという事実を強く認識するようになった。
認識するだけでなく、あらゆる助言を受けるに際して、それがモアベターな選択肢であるのか。
常に自問自答する癖をつけようと心がけ、そして「素直な疑問」にも積極的に従うことを忘れないようにしている。
常識的に考えてなにかおかしい。
素直に考えると、その選択肢はない。
専門家の言うことであってもそう思えば、必ずその理由を聞き、納得するまで決断を下さないことだ。
当たり前の話だが、税金の申告漏れを税理士のせいにしても、追徴課税は免れない。
契約書の不備を弁護士の力不足として怒ったところで、契約相手には無関係である。
経営者にとって、全ての決断のリスクは専門家ではなく、自分に帰ってくるのだから当然の話である。
そしてこのケースでは、常識的な感性に従った結果、3億円の案件が10億円に化けた。
経営者の感性と決断はこれほどまでに、株主や従業員の人生を大きく変える可能性があるという、非常にわかりやすい事例なのではないだろうか。
拙い経験談であったが、マネジメント層にある方の参考として、お役に立てるネタであれば嬉しく思う。
[adrotate group=”15″]