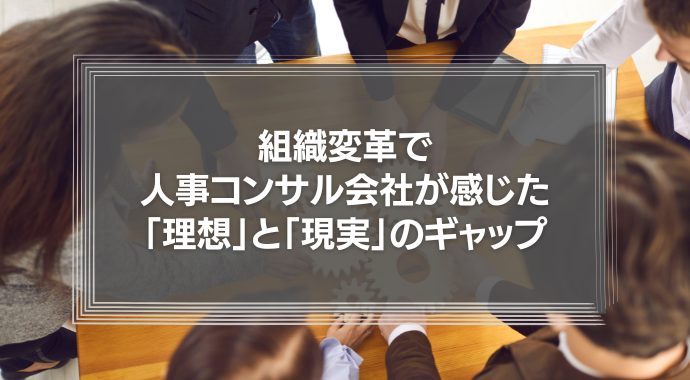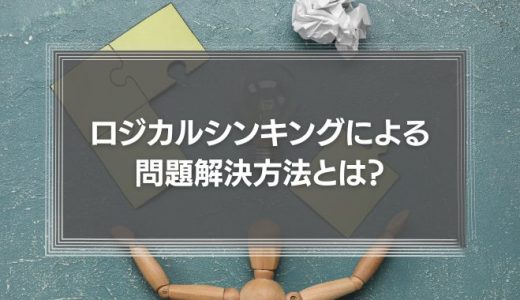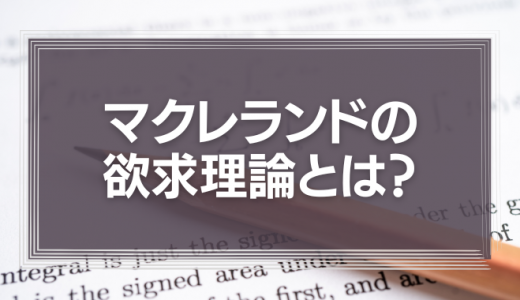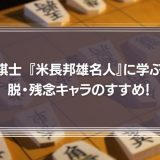昔、人材育成や、人事評価のコンサルティングをやっていたことがあります。
多くの会社を見ましたが、仕事を依頼してくる会社の動機は様々でした。
成果主義という名のもとに、なんとかして人件費を削ろうとする会社。
これはほぼ、リストラと同義です。
猛烈な反対勢力を生み出す一方で、多くの社員は無関心でした。
また、結構見られたのが、社員同士の交流を増やして、コミュニティを活性化したいという会社。
改善活動をやるのですが、社員間の温度差が激しく、大抵は一部の人が盛り上がるだけ、というケースが多かったように感じます。
さらに、事業が大きく変化したので、評価基準もそれに合わせて大きく変えたい、という会社もありました。
古参と若手のいがみ合いをどう収めるか、新社長の最初の試練となりました。
ピラミッド型組織をプロジェクト型の組織に変えるため、従来の固定的な管理職を撤廃した会社もありました。
流動性の高いリーダー職を設定し、才気あふれる若手がやる気を出した一方、
創業当時からのメンバーが冷や飯を食うことになり、社長との間に深刻な溝ができてしまいました。
こうして、いろいろな会社の人事組織の施策を思い出すたびに、組織とは
千差万別であり、人間の思惑が生々しく表出するのだな、と感じました。
<<あわせて読みたい>>
メタバースとは?メタバースの語源や意味、具体例をわかりやすく解説!
DXとは?デジタルトランスフォーメーションの意味や定義をわかりやすく解説
目次
「組織論」は役に立つか。
さて、そうした中。
一定数、「組織論」あるいは、組織論から派生する最新の組織形態に興味を持つ会社があります。
少し前だと、「ティール組織」あるいは「ホラクラシー」といったもの。
一昔前だと、マトリックス型組織やプロジェクト型組織など。
組織形態に関しても、常に流行り廃れが存在し、常に組織形態を模索することが好きな会社があります。
こうした会社は、組織コンサルティング会社の常連顧客ですから、セミナーや文献などにもよく登場し、組織改革の有効性についてPRされていることも少なくありません。
もちろん、コンサルティング会社のメッセージは
「常に組織形態をアプデすべし!」で一貫しています。
もちろん、そうでなければ、食いっぱぐれてしまいますからね。
しかしこうした「組織論」。
実際に役に立つのか、と疑問に思う方もいるでしょう。
「すごい効果があった」という方がいる一方で、「名前はかっこいいけど、実効性はない」とか「現実的ではない」という方も多く、なかなか判断に迷います。
また、次々と新しいコンセプトが現れては消え、何が正しいのかよくわかりません。
で。
いろいろな会社を見て、私が思ったことを述べますと。
「組織論が役に立つ会社はある。だが、ほとんどの会社にとっては組織論は難しすぎる」
といってよいと思います。
組織論自体は、学者などが考えたものですので、理論として整合性はとれています。
ただし、現実の組織にそれを適用する、となると、途端に困難が伴います。
実際には、そこそこ真面目に取り組んだとしても、「組織論」で掲げていた理想には程遠く、革新的な組織改革どころか、現状追認で若干の修正が施される程度、というのがほとんどでした。
多くの皆様にも覚えがあるのではないでしょうか。
なぜでしょう。
それは、「組織の中で働く人間の認識能力が、組織論の提示する理想についていけないから」です。
ですから、組織論の現実への適用は、そうとう難しい。
注意すべきは、組織論は「理解できない」のではないという点です。
「理解はできる、だが実行はできない。」
これが本質です。
これは、いつの時代でもそうでした。
というのも、
組織論は、人間に対して、認識の変化、つまり自己変革を要求するからです。
例えば、PCやスマートフォンを使うのに、自己変革の必要はありません。
かんたんな操作法さえ覚えれば、すぐに誰でも使えるようになります。
(それでも一定数は拒否する人がいますが)
ところが、組織論はそうした便利な道具の数々と同じような「単なるツール」ではないのです。
組織論は、一種の思想ですから、その思想が定める規律に従った行動変容を要求します。
それはある意味「宗教」に近い。
だから、コンサルを呼びつけて「ティール組織を作れ」といって、実現できるような性質のものではないのです。
具体的に話をしましょう。
例えば、上で挙げた「ティール組織」。
提唱者のフレデリック・ラルーによれば、ティール組織における人のありようは、以下のようなものです。
進化型(ティール)では他人から認められること、成功、富、帰属意識は快楽的な体験であり、エゴを充足させる甘酸っぱい「わな」ととらえられる。
そのため、それ以前の段階とは対照的に、優先順位が入れ替わる。良い人生を送るためには他人からの評価や成功、富、帰属意識を求めず、充実した人生を送るよう努める。
他人から認められることや成功、富、愛は結果にすぎない。
(ティール組織 英知出版)
言っていることはわからなくはありません。
しかし、これを全員が「腹落ちした」と言っているような組織を私は見たことがないですし、当面は存在もしないでしょう。
私が「宗教的」と表現した理由がわかると思います。
あるいはシステム思考でしられる著作「学習する組織」で、ピーター・M・センゲが、学習する組織を作り上げるために提唱した、「自己マスタリー」という思想は次のようなものです。
自己マスタリーは、能力やスキルを土台にしているが、それらにとどまるものではない。精神的な成長を必要とするが、心を解き明かす、あるいはオープンであることにとどまるものでもない。
それは、独創的な仕事として自分の人生に取り組み、受身的な視点ではなく、創造的な視点で生きるということなのだ。
(学習する組織 英知出版)
「意識高すぎー」と感じる方もいると思いますが、提唱者は大まじめに、変革のための条件としてこれを提示しています。
こうした「精神的な成長」「自己変革」を一介の企業が成し遂げようとしたときに起きる摩擦は、想像に難くありません。
人間は考えを変えたがらない
単純に言えば「組織変革」とは、従業員をこうした思想、あるいは規律に従わせることにほかならず、組織論とは、その思想の種類を述べているに過ぎません。
しかし、多くの人は自分の考え方を変えることを良しとしません。
「失敗の科学」を著したマシュー・サイドは、
また、自分に自身がある賢い人ほど、自分の間違いを認めたがらない傾向があると述べています。
ダートマス大学の経営学教授、シドニー・フィンケルシュタインは、名著『名経営者が、なぜ失敗するのか?』で、致命的な失敗を犯した50社強の企業を調査した。
すると組織の上層部に行けば行くほど、失敗を認めなくなることが明らかになった。皮肉なことに、幹部クラスに上がるほど、自身の完璧主義を詭弁で補おうとする傾向が強くなる。
その中でも、通常一番ひどいのがCEOだ。
たとえば我々が調査したある組織のCEOは、45分間の聞き取りを通してずっと、会社が被った災難がいかに自分以外の人間によりもたらされたかを並べ立てた。矛先を向けられたのは顧客、監査役、政府、さらに身内である自社の重役たち。
しかし自身の過失については一切言及がなかった。
自分の判断は賢明だったとひたすら信じ、それに反する事実を突き付けられると自己弁護に走る。原因は、もはや言うまでもない。
認知的不協和の影響で目の前が見えず、最も失敗から学ぶことができていないのは、最も失うものが多いトップの人間なのだ。(失敗の科学 ディスカヴァー・トゥエンティワン)
旗振り役である組織のトップの多くが「考えを変えたがらない」状態では、当然、組織の変革などありえません。
京セラの創業者である稲盛和夫氏は、しばしば「宗教的」と評価されます。
しかし、ある一つの規律や思想に沿って、組織を運営しようとすれば、それはある意味、当然のことでもあります。
結局のところ、人間の思想は非常に惰性が強く、組織論を導入すること、つまり新しい思想の導入は恐ろしく時間がかかります。
そのような実情から、組織形態や組織論は、新しいものに飛びつくのはやめておいたほうがいいでしょう。
むしろ、経営陣や幹部が、ある意味その職業人生かけて、一つか二つ、変革が可能なものだ、と考えておいたほうがよさそうです。
組織変革がうまくいくのは「細かいルール」を積み重ねたとき
対照的に、組織変革がうまくいっている会社は、一気に社員の思想を変えようとせず、
「小さなルールの適用」を、細かく繰り返すことで、組織への思想の浸透を図っています。
例えば
「遅刻は許さん」とか「依頼を出すときは必ず納期を決めよ」、あるいは「日報は定められた形式で書け」といった具合です。
実際、キリスト教やイスラム教の源流であるユダヤ教には、旧約聖書に様々なルール、すなわち戒律が定められています。
神の名をみだりに唱えるな、週一回の安息日には働くな、殺すな、盗むな、姦淫するな、隣人のものを欲しがるな。
そうした細かなルールを守らせることで、「思想の浸透」を図る。
このほうが、「組織論」を一気に適用して、組織変革を図るよりも、はるかに実効性があり、また堅牢な組織が実現します。
したがって、組織を預かる者が知らねばならないのは、
組織論 → ルール設定 という演繹的なプロジェクト推進よりも
ルール設定 → 組織論 という帰納的なプロジェクト推進をすべき、という話なのです。
<<あわせて読みたい>>