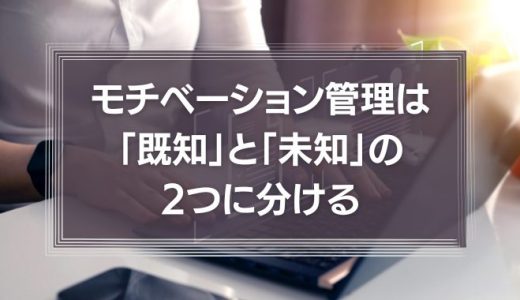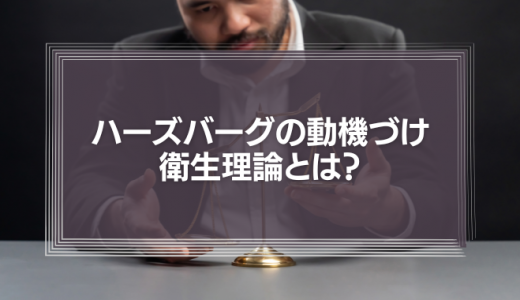高市早苗氏が「ワークライフバランスという言葉を捨てる」と発言し、働き方をめぐる議論が一気に広がりました。
ここで論じたいのは政治的な是非ではありません。この発言が話題になったという事実そのものです。
同じ構造の違和感は、企業の現場でも繰り返し表面化しています。
それが「ワークライフバランス」という言葉です。
経営者であれば、一度はこんな場面に出くわしているのではないでしょうか。
「ワークライフバランスを重視したい」という言葉が強調される場面では、成果や責任についてのコミットが忘れ去られていると感じることがある。
その一方で、結果を出し続けている社員ほど、働き方そのものについて多くを語らないように見える、といった印象を持つ経営者もいるでしょう。
このズレに、多くの経営者は言語化できない違和感を抱いています。
今回話題になった次の主張は、過激に見えるかもしれません。
ワークライフバランスって言ってるやつで優秀なやつ1人も見た事がない。
仕事ができない市場価値が低いやつほどこの言葉をよく出してくる。
引用:https://x.com/kazumasa_Seko/status/1995055615933022618
ただし、ここで述べられているのは、個人の好き嫌いや感情的な評価ではありません。
このした認識を前提にした場合に、どのような行動や結果が生じやすくなるのか、そのメカニズムについて述べたものです。
なぜこの言葉に、多くの経営者が腹落ちするのか。その理由は、識学の理論で驚くほど明確に説明できます。
目次
識学が前提とする、避けられない現実
識学の出発点はシンプルです。
人は事実そのものではなく「自分がどう認識しているか」に基づいて行動します。
そして、成果が出ない原因の多くは、能力不足や努力不足ではありません。前提となる認識のズレにあります。
たとえば、「成果を出す前から、業務上の裁量や働き方に関する配慮が成果を出した社員と同程度に与えられる」と思い込むことです。
この認識を前提にすれば、人は自然と責任を回避し挑戦を避ける行動を取ります。
人は与えられた前提の中で、自分なりに最も合理的だと思う行動を選びます。
そのため、前提となる認識がずれていれば、本人に悪意がなく仕事に対して真剣であっても、選択する行動は組織の期待とは異なる方向に向かいやすくなります。
たとえば、本来は成果や責任を優先して判断すべき場面でも、働きやすさや負担の軽さを基準に行動を選んでしまう。
これが、識学でいう「行動のズレ」です。
この考え方を前提にすると、ワークライフバランスという言葉が組織にどのような影響を与えるかは分かりやすくなります。
ワークライフバランスが生む致命的な誤認識
ワークライフバランスという言葉は、無意識のうちに次の前提を刷り込みます。
- 仕事と人生は最初から等しい価値を持つ
- 成果を出す前からバランスを求めてよい
- 働きすぎないことは無条件で正しい
これらは一見すると優しい考え方に見えますが、市場原理とは正面から衝突します。
市場は、個人の感情や努力そのものを評価する仕組みではありません。評価の対象になるのは、あくまで成果です。
成果を継続的に出している人材には、業務の進め方や役割について、周囲との調整や裁量の余地が生まれやすくなります。
また、その人が生み出す価値が明確であるほど、働き方や役割についても一定の交渉が可能になります。
成果によって価値を示した人ほど、発言権が強くなるので働き方に関して選択の幅を持ちやすくなるといえるでしょう。
識学では、評価の基準を結果に置きます。もちろん、一般的な組織では努力やプロセスが評価される場面もあります。
ただし、努力そのものが評価の中心になると、成果との関係が曖昧になり組織の判断基準が不明確になりがちです。
この状態は組織の競争力を低下させ、いずれ市場から退場することを余儀なくされるでしょう。
組織は結果を重視せざるを得ないのです。
努力そのものが評価されるわけではありません。苦労が報われるわけでもありません。評価されるのはあくまで結果です。
この現実を直視し、結果を出さない限りワークライフバランスは絵に描いた餅になってしまいます。
なぜ「できる人ほどワークライフバランスを語らないのか」
本当に仕事ができる人ほど、ワークライフバランスという言葉を使いません。
彼らが語るのは、
- どこまで責任を持てるか
- どこまで任せられるか
- どうすれば成果を最大化できるか
といったことであり、労働時間や休日の話ではありません。
理由は単純です。すでに選択権を持っているからです。
市場価値を上げ切った人間は自分で「設計」できるため、バランスを「要求」する必要がありません。
一方で、ワークライフバランスを強く主張する人ほど、その選択権をまだ持っていません。
これは能力の問題ではなく順序の問題です。
「バランス」はゴールであって、スタートではない
次の一文は、極めて識学的です。
血と汗と涙を流し、市場価値を上げ切った先に真のワークライフバランスが待っている
引用:https://x.com/kazumasa_Seko/status/1995055615933022618
識学では、順序を何より重視します。
責任 → 結果 → 評価 → 裁量
この順番を飛ばした瞬間、組織も個人も必ず歪みます。
・結果を出す前に自由を求めること。
・価値を示す前に権利を主張すること。
それは主張ではなく、認識の逆転です。
ワークライフバランスは否定されるべき概念ではありません。
ただし、それはゴールであって、スタート地点に置いてよいものでもないのです。
識学でいう「責任」と「自由」を履き違えた瞬間、成長は止まる
識学では責任と自由は必ずセットで扱われます。
なぜなら、組織において自由や裁量とは判断の結果について責任を負うことを前提に与えられるものだからです。
自由や裁量だけ与えたら個々人が自分勝手に行動し、組織は崩壊してしまいます。
ワークライフバランスを前提にした働き方は、この原則に完全に反しています。
「責任は最小限で自由は最大限ほしい」
このような認識が組織の中で共有されるようになると、個人の成長は停滞し、組織全体の競争力も低下してしまうのです。
なぜ「若手のワークライフバランス」は怠惰に変わるのか
識学は、人を性善説や性悪説といった価値判断で捉えません。
人は誰しもできるだけ負荷を避け、楽な選択を取りやすいという自然な性質を持っていると考えます。
これは人間の欠点を指摘しているのではなく、人だけでなく多くの生き物に共通する、当たり前の前提です。
ただし、この性質を前提として扱わず仕組みやルールで制御しないままにしてしまうと、組織のパフォーマンスは徐々に低下していきます。
その結果、業績が悪化しリストラや倒産といった形で、最終的には働く人自身に不利益が及ぶことになります。
だからこそルールが必要であり、評価基準が必要であり、成果と責任を結びつける必要があります。
成果や責任の前提が整理されないまま語られるワークライフバランスの多くは、
- 自分の成果を測らない
- 市場との比較をしない
- 将来の価値より、今の快適さを基準にする
という誤った前提の上に成り立っています。
たとえば、「成長したい」といいながら、責任が増える業務や難易度の高い案件は避けるようになってしまいます。
個人の意欲や姿勢ではなく行動の前提となっている認識のあり方なのです。
組織で起きる「静かな崩壊」は善意から始まる
経営者は善意で言います。
「無理しなくていい」
「プライベートも大事にしてほしい」
しかし、成果基準を示さずにこの言葉だけが先行すると、現場では別の意味として受け取られてしまいます。
具体的には「責任の重さは問われない」「結果が出なくても大きな問題にはならない」といった認識に置き換えられてしまうのです。
識学は、この状態を最も危険だと捉えています。
経営者が勘違いしてはいけないこと
ここで誤解してはいけないのが、「長時間労働を礼賛しろ」という話ではないという点です。
識学が否定するのは、
- 成果につながらない努力
- 目的のない我慢
- 感情論による根性論
です。
問題は、成果と切り離されたワークライフバランス思想が、組織の前提になってしまうことです。
それは社員の成長を止め、最終的には企業の競争力を奪います。
優しさが組織を壊す前に
ワークライフバランスという言葉は耳障りがいい言葉です。
しかし、経営者がそれを無条件に受け入れてしまうと、組織の中で「何を優先すべきか」という判断基準が、少しずつ曖昧になっていきます。
識学は、厳しく見える考え方だといわれることがあります。
しかしそれは、人や組織の将来にとって何が本当に必要かを見誤らないためです。
成果や責任の基準を明確にすることは、短期的には冷酷に感じられるかもしれませんが、結果としてお互いの利益になるのです。
- 成果が先
- 価値が先
- 自由は後
この順序は経営者が言語化し、組織の前提として共有する必要があります。
ワークライフバランスは否定されるべき概念ではありませんが、努力と成果を積み重ねた先に成立するものであり、経営者はそれを最初から前提として扱ってはいけないのです。