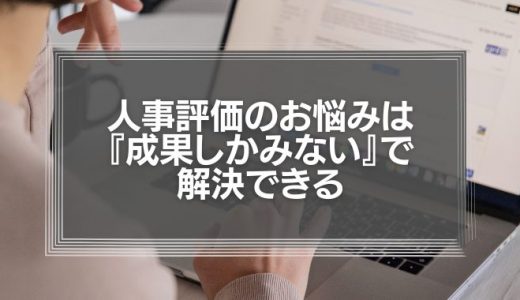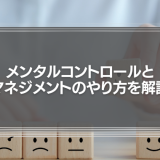「残業代ゼロ法案」とも呼ばれる「高度プロフェッショナル制度」は、労働者にとってネガティブな側面が強調され、国会やメディアで議論されています。
マイナスの面ばかりが話題になっている制度ですが、この制度の本質は労働者の残業代をゼロにすることではありません。労働賃金を「時間」ではなく「成果」で評価することで、日本の労働環境を改善していくことが目的の制度となっています。
2019年4月より施行されたこの制度や考え方は、将来的に形を変えながら労働者の中で広がっていくことが予想されるため、自社での導入の如何にかかわらず本質をしっかり理解しておくことが大切です。
今回は、高度プロフェッショナル制度の内容や導入に関する注意点などについて徹底的に解説していきます。
<<あわせて読みたい>>
メタバースとは?メタバースの語源や意味、具体例をわかりやすく解説!
DXとは?なぜDXと略すの?デジタルトランスフォーメーションの意味や定義をわかりやすく解説
目次
高度プロフェッショナル制度とは
高度プロフェッショナル制度の内容
高度プロフェッショナル制度とは「高度の専門的知識等を有し、職務の範囲が明確で一定の年収要件を満たす労働者を対象として、労使委員会の決議及び労働者本人の同意を前提として年間104日以上の休日確保措置や健康管理時間の状況に応じた健康・福祉確保措置等を講ずることにより、労働基準法に定められた労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定を適用しない制度[1]」のことです。
簡単に言うと「特定の職種の労働者を労働時間規制の対象から除外する制度」のことを指しています。
結果さえ出せば短い労働時間で報酬が得られる一方で、残業時間に対する規制がないところがデメリットです。「過労死が増える制度」および定額で残業させ放題になる「残業代ゼロ制度」と、施行された今でも論争が続いています。
同制度には問題も含まれていることは事実ですが、この記事では制度の是非については論じません。制度の本質や、その本質がこれからの企業経営と人材マネジメントにどう関連するかについて以下で考察していきます。
高度プロフェッショナル制度の本質
高度プロフェッショナル制度の本質は、以下の2つです。
- 低いとされる日本のホワイトカラーの労働生産性の向上
- アップルを始めとするアメリカ企業のような独創的、創造性のあるビジネスモデルや製品・サービスの開発を可能にすること
従来の日本における労働環境では、長時間労働や残業をした労働者が、そうでない労働者と比べて高額な賃金を得られる仕組みになってしまっています。そのため、残業代目当ての非効率的な長時間残業も多いのが現状です。
高度プロフェッショナル制度のもとでは、労働時間と報酬がリンクしていません。ゆえに、労働者には短時間で成果をあげようとするモチベーションが働き、労働生産性の向上が期待できます。また、成果に応じて報酬を変えることで、従業員に成果を出そうとする意欲が生じて業績のアップにつながります。
同制度に多くの問題点が内在していることも事実ですが、その本質を企業経営・人材マネジメントに取り入れる考えや視点を持つことは重要なことです。
高度プロフェッショナル制度とその他の労働方法を比較
高度プロフェッショナル制度と似た制度に、「裁量労働制」や「フレックスタイム制」があります。
それぞれの制度・働き方にはどのような違いがあるのでしょうか。
高度プロフェッショナル制度と裁量労働制との違い
高度プロフェッショナル制度と裁量労働制はよく似ており、比較されることも多い制度です。各制度の特徴について見ていきましょう。
裁量労働制
実務労働時間ではなく、あらかじめ労働者と企業との間で定めた「みなし労働時間」を給与支払いのベースとします。みなし労働時間以上の時間仕事をしても、残業代などは支払われません。
法定労働時間は週に40時間ですが、みなし労働時間が法定労働時間を超えている分は、残業代として支払われる仕組みです。例えばみなし労働時間を週5日9時間と決めた場合、週の労働時間は45時間になるので、5時間は残業代がついた形で支払われます。この場合、5時間以上残業をしても追加で残業代が出ることはありません。
また裁量労働制では、深夜勤務や休日勤務に手当がつくようになっています。このように、裁量労働制には「労働時間」という概念が存在しています。
高度プロフェッショナル制度
高度プロフェッショナル制度には「労働時間」という概念は完全になく、労働基準法の定める法定労働時間や休憩、休日の規制が一切適用されません。労働時間にかかわらず、一定の給与で一定の成果を出さなくてはならない働き方になります。
極端な話をすると「10個の業務をこなすのに週に80時間かかる」Aさんも「同じ業務を20時間で終わらせられる」Bさんも、支給される給与額は同じになるのです。
高度プロフェッショナル制度とフレックスタイム制との違い
高度プロフェッショナル制度とフレックスタイム制との間でも、労働時間概念の有無が大きな違いとなっています。
フレックスタイム制
フレックスタイム制とは、「精算期間(1ヶ月以内の一定期間)」の労働時間をあらかじめ定めておき、その枠内で自由に労働する制度です。
始業時間及び就業時間を自主的に定められ、規定の時間以上働くと残業代が発生します。また、精算時間以内であっても深夜勤務をした場合は手当が発生します。
高度プロフェッショナル制度
高度プロフェッショナル制度では、労働時間に規定は一切ありません。何時間働いても残業代は出ませんし、労働時間が少なくても成果さえ出ていれば報酬は出ます。深夜に働いても深夜手当が出ることもないため、どんな働き方をしても定められた一定の報酬しか得られません。
アメリカのホワイトカラーエグゼンプション
日本の高度プロフェッショナル制度のモデルとなっているのが、アメリカのホワイトカラーエグゼンプションシステムです。
ホワイトカラーエグゼンプションシステムでは、オフィスで仕事をするホワイトカラー労働者を対象に、労働法の規制を緩和・免除する制度のことです。
週給455ドル以上(アメリカでは週給で給与支払する会社が多い)で、業務の1割でも対象職種に該当していればホワイトカラーエグゼンプション対象となり、企業側が残業代を支払わなくてよいことになっています。
企業側からすると、労働者がほとんど専門業務をしていなくても残業代を支払わなくても良いというメリットがあります。そのため、雇用者によるホワイトカラーエグゼンプションの強要が問題になっているのです。
現在、アメリカのホワイトカラーエグゼンプションシステムでは、給与規定や職務要件の見直しが検討されています。[2]
高度プロフェッショナル制度の概要
高度プロフェッショナル制度の適用の条件
高度プロフェッショナル制度は、一定の条件を満たした労働者のみに適用される制度です。高度プロフェッショナル制度の適用条件や構成は以下の通りです[3]。
対象業務
①金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
②金融知識等を活用した自らの投資判断に基づく資産運用の業務又は有価証券の売買その他の取引業務
③有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務
④顧客の事業の運営に関する重要な事項についての調査又は分析及びこれに基づく当該事項に関する考案又は助言の業務
⑤新たな技術、商品又は役務の研究開発の業務
年収要件
年収1,075万円以上の労働者
※確定額で、賞与や手当、残業代を含まない金額
健康管理時間の把握
①「対象労働者の健康管理時間」を把握する措置を使用者が実施すること及び当該事業場における「健康管理時間の把握方法」を決議で明らかにする。
②健康管理時間を把握する方法は、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法による必要がある。ただし、事業場外において労働した場合であって、やむを得ない理由があるときは、自己申告によることができる。
③日々の健康管理時間の始期及び終期並びに健康管理時間の時間数を記録するほか、医師の面接指導を適切に実施するため、1ヶ月当たりの時間数の合計を把握する必要がある。
休日の確保
*対象労働者に年間104日以上かつ4週間を通じ4日以上の休日を与え、決議で休日の取得の手続を具体的に明らかにする。
法選択的措置
次のいずれかに該当する措置を決議で定め、実施しなければなりません。
①勤務間インターバルの確保(11時間以上)+深夜業の回数制限(1ヶ月に4回以内)
②健康管理時間の上限措置(1週間当たり40時間を超えた時間について、1ヶ月について100時間以内又は3ヶ月について240時間以内とすること)
③1年に1回以上の連続2週間の休日を与えること(本人が請求した場合は連続1週間×2回以上)
④臨時の健康診断( 1週間当たり40時間を超えた健康管理時間が1ヶ月当たり80時間を超えた労働者又は申出があった労働者が対象)
詳細は、政府関連機関の資料(高度プロフェッショナル制度 わかりやすい解説 厚生労働省)を参照してください。
参照:「高度プロフェッショナル制度 わかりやすい解説」(厚生労働省)
労働基準法の歴史
高度プロフェッショナル制度や労働者とは切っても切り離せない法律として、労働基準法が挙げられます。そもそも労働基準法はどのような経緯で成り立った法律なのでしょうか。ここからは、労働基準法の歴史を簡単にご紹介していきます。
労働基準法が制定されるきっかけとなったのは、アメリカの労働運動の記念碑的な出来事“May Day”です。
1886年5月1日、長時間労働で苦しむアメリカの労働者が8時間労働を要求して約35万人がストライキに立ち上がったことが、メーデーの起源です。
参照:「メーデー」(wikipedia)
日本での労働基準法は、戦後日本の占領軍(GHQ:General Headquarters)による改革の一環として制定されました。注目しなければならないのは、軍国主義の復活を防いで「アメリカの国際的な優位性を築くための労働環境」にメスを入れるために労働基準法が制定された事実です。そのキーストーンとなるのが「労働時間の短縮」でした。
2017年の日本の産業構造は第三次産業が全体の72.8%を占めており、第一次産業が3.4%、第二次産業が23.8%という構成比です。労働基準法の制定された時代(最初の統計1951年、31.4%、46.1%、22.6%)と様相が異なります(総務省「労働力調査」)。
この第三次産業に属する高度プロフェッショナルは「知識労働者」(P.F.ドラッカー)であり、労働基準法ができた当時の労働者と質的に大きな変化があります。
時代や労働者の質の変遷とともに法律や労働環境を変化させていくのは、当然のことだと言えるでしょう。
高度プロフェッショナル制度の対象になる職種
さて、前項で高度プロフェッショナル制度の適用条件を説明しましたが、具体的にどんな職種が該当するのかが分かりにくかったかと思います。高度プロフェッショナル制度の適用条件に該当する具体的な対象業務は、以下のようなものになります。
金融アナリスト
企業や市場の高度な分析業務
金融業務の開発業務
金融工学や統計学、経済学などを含む専門知識でシミュレーションや検証を行いながら行う金融商品の開発業務
金融商品のディーラー
資産運用業務や有価証券の売買、証券会社における専門知識が必要となるディーラー業務
コンサルタント
企業業務に関する企画や立案、運営の高度な分析、助言などを行う業務
新技術などの研究開発
新しい技術や商品、役務の研究開発。または、新しい技術を用いた管理方法の構築やサービスの研究開発業務。
以上の業務に従事していて、年収1,075万円以上の労働者が高度プロフェッショナル制度の対象者となります。
ただし、上記の業務に従事していても「調査や分析のみを行う」「指定された指示に従う業務」「既存の技術等組み合わせた開発」などの場合は高度プロフェッショナル制度の対象となりません。対象となり得る業務については、厚生労働省の資料をご参照ください。
参照:「高度プロフェッショナル制度 わかりやすい解説」(厚生労働省)
高度プロフェッショナル制度の対象にならない職種
高度な専門知識を持つ職種として医師や公認会計士が挙げられますが、この2つの職種は高度プロフェッショナル制度の対象職種には該当しません。高度プロフェッショナル制度は業務時間に縛られない働き方を実現する制度で、医師や公認会計士は労働時間を自由に設定できないためです。
ただし、研究開発を行っている研究医やコンサルティング業務を担当している会計士は対象になる可能性もあります。
高度プロフェッショナル制度の対象となる業務の線引きは、まだまだ曖昧な部分も多いです。これから制度が普及されていくにつれて、徐々に明確になっていくことが予想されます。
高度プロフェッショナル制度の導入には企業のマネジメント力が必要
メリットだけではなくデメリットも多く考えられる高度プロフェッショナル制度。「ワーク・ライフバランス」社長の小室氏のコメントにもあるように、この制度を導入する際には企業と管理職のマネジメント力が必要となります。
高度プロフェッショナル制度の導入にともなって必要となる企業のマネジメント力には、以下のようなものが挙げられます。
業務の棚卸
現状の業務内容や業務量・配分にそのまま高度プロフェッショナル制度を適用すれば、過労死の問題を払拭することはできません。業務の棚卸を行うことで、労働者が本来の「やるべき」業務に集中することができるようになります。
仕事の取捨選択
やらなくてよい業務や、これまでの惰性で続けているような業務はありませんか?少しシステムを変えるだけで不要になる業務は、実はたくさん存在します。
業務を取捨選択して業務のスリム化を図らなければ、本来やるべき業務が埋もれてしまいます。その状態で高度プロフェッショナル制度を導入することは、労働者にとって非常に酷といえるでしょう。
仕事の振り分け
従業員に「何事も経験だから、とりあえずこの仕事やってみて」と、多種多様な業務をさせていませんか?
高度プロフェッショナル制度では、労働者へ無際限に業務を振り当てないように「特定の業種に従事する労働者への決められた業務」を規定しています。コンサルタント業務に従事しているにもかかわらず、本来の業務とかけ離れた経理事務や営業の仕事をさせているようでは、高度プロフェッショナル制度導入までの道のりは長いと言えるでしょう。
労働者の意識改革
高度プロフェッショナル制度は、これまでの「労働時間」という概念が全くない新しい働き方です。労働者の意識を変えなければ、時間をかけて高度プロフェッショナル制度の導入を検討したとしても徒労となってしまうでしょう。
長時間労働との決別
高度プロフェッショナル制度は、「一定の成果に対して報酬を支払う」という考えを基に成り立っています。しかし日本では、長時間労働することが会社への貢献と考えている労働者も多いのが現状です。高度プロフェッショナル制度はその考え方とは相反するもののため、長時間労働に対する意識を変えていく必要があるのです。
会社方針として長時間労働との決別を示さなければ、高度プロフェッショナル制度の導入は難しいと考えられます。特にマネジメントのカギとなる管理職には、「限られた時間で最大の成果を出す」スキルと意識が必要です。
仕事に対する自主性を養成
高度プロフェッショナル制度では「指示されるのではなく、自主的に仕事を行うこと」が求められています。しかし、自主的に仕事をした結果が会社の意図ややるべきことと異なっていたら問題です。
指示待ちをせずとも、会社の意図に沿った業務を自主的にできるような社員の教育及び養成が欠かせないのです。
高度プロフェッショナル制度への理解
高度プロフェッショナル制度について、経営者自身も不明な点が豊富でしょう。しかし、分からないまま自社に導入してしまえば、完全な見切り発車になりかねません。経営者自身が間違った運用をしないよう、勉強会などに参加する必要があります。
また、社員の制度理解が不十分であると、制度適用社員とそうでない社員の間に見えない溝ができてしまう可能性が高いです。自分は8時間の労働をしているのに、5時間しか働いていない社員が自分よりも高給を取っていたら、普通であれば良く思いませんよね。
会社はチームワークが命です。チームの輪を乱さないためにも、社員の中にも高度プロフェッショナル制度の理解を浸透させる必要があります。
業務の見える化を推進する
業務の進捗管理は、高度プロフェッショナル制度にかかわらず必要なことです。業務の棚卸や高度プロフェッショナル制度を適用する社員の進捗管理、そして場所を選ばずに仕事をしてもらうためにも、業務の見える化推進は大切な事前準備といえるでしょう。
業務の見える化とは具体的にどのようなものなのでしょうか。その内容を見ていきましょう。
業務進捗を共有する
労働において、業務の進捗を共有することは非常に大切です。高度プロフェッショナル制度で高給を払っているにもかかわらず、進捗について全く見えない状態で労働させていれば、1年経っても結果が出てこない事態になってしまう可能性もあります。また上司が進捗を把握していなければ、労働者から相談を受けても適切な回答ができません。
適度にミーティングの機会を設ける、あるいは業務進捗を確認できるツールを採用するなど、進捗確認ができるシステムを確立しておきましょう。
文書の電子化を推進する
「重要文書は紙体でしか保存していないので確認のために出社する」となると、高度プロフェッショナル制度の自由性が奪われてしまいます。しかしながら、自宅で社外秘の文書を印刷される、外部PCからのアクセスで会社のシステムがウイルスに感染するなどといった事態に陥ってしまえば、元も子もありません。
文書の電子化を推進しつつ、専門家の力を借りてセキュリティ強化を行うことが好ましいでしょう。
業務のマニュアル化
業務のマニュアル化を行うことによって、各業務の中身が見えるようになります。中身が見えるようになると無駄な作業も可視化でき、業務の棚卸にも役立つでしょう。また、業務の進捗が理解しやすくなり、社員同士の業務への理解が深まります。
高度プロフェッショナル制度は労働者の「成果の基準」がカギ
高度プロフェッショナル制度を実際に現場で活かすためには、どのような運用が望ましいのでしょうか。以下では、マネジメントで高度プロフェッショナル制度を活かすための考え方を解説します。
高度プロフェッショナル制度のカギは「成果の基準」
高度プロフェッショナル制度を活用して労使双方にメリットのある「新しい働き方」を実現するためには、まず対象となる労働者一人ひとりの「成果の基準」を設定しなければなりません。
成果の基準が明確になってこそ、労働者は「早く仕事を終わらせて帰ろう」という気持ちになり、現場のマネジメントも「ちゃんと仕事を終わらせてから帰っているな」と評価を下せるようになります。「どこまで会社の仕事をしていれば問題ないか」が明確になれば、労働者の成果を適切に判断できるようになるでしょう。
例えば「今月は進行中の研究プロジェクトの進捗度を15%にする」ということを成果の基準とすれば、日々の仕事の量もおのずと決まってきます。
一方で成果の基準が「今月は現在進行中の研究プロジェクトに全力を尽くす」のようなあやふやな内容だったとしましょう。この場合、労働者が「仕事が終わった」と判断しても、上司が「まだ終わっていない」と評価すれば、労働者は際限なく会社に拘束されます。成果の基準があやふやになると、高度プロフェッショナル制度が抱える長時間労働のリスクが表面化するのです。
したがってこの制度を運用するマネジメント側は、「成果の基準」を明確にして労働者と認識を合わせる必要があります。
明確な成果の基準は「期限」と「数値」で作る
明確な成果の基準は、「期限」と「数値」によって作られます。
例えば、先ほどの「今月は進行中の研究プロジェクトの進捗度を15%にする」には、「今月」という期限と「15%」という数値が盛り込まれていますよね。これを「現在進行中の研究プロジェクトを進める」にすると、あっという間に何が「成果」になるのか分からなくなります。
「期限が決められない仕事や、数値化できない仕事もある」と言いたいマネジメント層の人もいるでしょう。しかし、期限設定や数値化が難しい仕事であっても、やり方次第で成果の基準は明確にできます。
現時点で期限が決められない仕事があるなら、その期限を決める期限を設定しましょう。直接売上や利益にならないような仕事も、業務をリスト化して達成度や進捗率として数値化しましょう。成果の基準が明確化されれば、高度プロフェッショナル制度は正しく運用できることでしょう。
やってはいけないのは、「頑張り」や「モチベーション」で評価することです。マネジメントは「君は数字を残しているが、頑張りやモチベーションが足りないから帰らずに働きなさい」と、成果以外の面で評価を下してはいけません。
なぜなら「頑張り」「モチベーション」による評価は、マネジメント側の主観でしかないからです。評価に主観をはさめば、労使双方が「成果」に関する認識を一致させることは不可能です。結果、高度プロフェッショナル制度のデメリットが表面化してきてしまいます。
高度プロフェッショナル制度の導入には、徹底して「期限」と「数値」によって成果の基準を明確化することが大事です。
高度プロフェッショナル制度の労働者のメリット
高度プロフェッショナル制度のメリットは「新しい働き方」の推進です。これは企業と労働者双方にとってのメリットだと考えることができます。
生産性の高い働き方
公益財団法人日本生産性本部の2017年版の調査「労働生産性の国際比較2017年度版」によれば、日本の時間当たりの労働生産性はOECD加盟国35ヵ国中20位、1人当たり労働生産性は同21位と低い水準です。[4]
高度プロフェッショナル制度は、生産性を引き上げる効果があると言われています。というのも、制度が適用されれば残業代が支払われなくなるため、労働者側は「いかに就業時間内に成果を出すか」を追求するようになるからです。すると労働生産性は改善され、労働者は「残業をせずに早く帰れる」、企業側は「無駄な残業代を支払わなくて済む」というメリットが生まれるわけです。
こうした働き方を制度面から後押しするのが、高度プロフェッショナル制度の役割の一つと言えるでしょう。
会社に縛られない、自由な働き方
労働者が生産性を上げ、労使間で「成果さえ出せば会社に8時間いる必要はない」という取り決めがあれば、「会社に縛られない、自由な働き方」を実現することも可能です。通勤に費やす時間や負担を減らし、出社をせずに自宅やカフェで働くことも可能になるのです。
こうした働き方の実践者は、実は非常に増加してきています。クラウドソーシング事業を展開するランサーズの「フリーランス実態調査 2018年版」によれば、副業・兼業や複業(パラレルワーク)を含む広義のフリーランスは、現在日本で1,119万人にも上っています。副業フリーランスだけを見ても、744万人に達しているといいます。[5]これは、日本で「会社にしばられない、自由な働き方」が一般化しつつある根拠となるでしょう。
しかし、会社側にとって従業員が「会社に縛られない」というのはデメリットでもあります。従業員が副業に精を出したり、副業の影響で業務のパフォーマンスが下がったりする可能性があるからです。
高度プロフェッショナル制度は、こうした会社側の不安をフォローする制度になり得ます。なぜなら、あらかじめ対象労働者が出すべき成果を決めておくことができるからです。「達成できない場合は副業を禁止する」と規定しておけば、パフォーマンスの低下が防げます。
この点から、高度プロフェッショナル制度は労使双方が安心して「会社に縛られない、自由な働き方」を実現する後押しになるのです。
人件費のカットが可能
従来までは、残業をすればするほど残業代が出て高額な給料がもらえるシステムだった日本。一方で成果主義である高度プロフェッショナル制度を導入すれば、労働者は残業をするメリットがなくなります。
仕事の効率アップを目指すようになるため、従業員も上司の早く帰ることが可能となります。結果として、余分な人件費だけではなく光熱費などの削減にもつながるのです。
高度プロフェッショナル制度の労働者のデメリット
メリットの一方で、高度プロフェッショナル制度を導入すると労働条件が悪化するリスクもあります。これについては労働者側のデメリットとして取り上げられることが多いですが、考え方によっては会社側のデメリットにもなるでしょう。
「働かせ放題」になるリスク
労働条件の悪化リスクを端的に表現すれば、労働者を「働かせ放題」になるということです。「休日の確保」や「健康・福祉確保措置」が規定されていますが、基本的には長時間労働をさせることが可能な制度となっています。場合によっては、「働かせ放題」が横行する可能性も十分にあるのです。
実際にアメリカのホワイトカラーエグゼンプションでは、残業代なしで雑務をさせ放題になってしまっている点が問題となっています。
アメリカのように、「無数にある業務を捌く残業をさせるため」に高度プロフェッショナル制度を導入することは、本来の趣旨とかけ離れた使い方となってしまいます。
業務・年収要件の拡大の可能性も
高度プロフェッショナル制度の対象となる業務・年収要件は、今後拡大される可能性があります。もしかしたら、年収400〜500万円程度のサービス業に従事する労働者にも、高度プロフェッショナル制度が適用される可能性があるかもしれません。[6]制度の適用には本人の同意が必須なため、同意せずに身を守ることも手段の一つです。
しかし、転職や独立へのハードルが高い業務を行う人に制度が適用されれば、「同意しない」という選択肢を取りにくくなってしまうでしょう。制度上は「同意しなかったからといって解雇その他の不利益な取扱いをしてはいけない」と規定しています。一方で、このルールにも明確な基準はなく、労働者が企業側からの嫌がらせ等を恐れて同意してしまう可能性があります。
こうした点から、高度プロフェッショナル制度が労働者を使いつぶすための制度になる危険性も十分あるのです。
考えなしに制度を適用すると会社側にもデメリットが生じる
制度の濫用が横行すると、会社側が高度プロフェッショナル制度を適用しにくくなるデメリットも生じます。
労働者側のメリットを考慮して制度を適用しなければ「あの会社は高度プロフェッショナル制度を適用して、労働者を酷使している」と評価されてしまうからです。そうなれば優秀な人材を採用できなくなり、業績は悪化するでしょう。現在のように多くの企業が慢性的な人手不足に悩まされている売り手市場であれば、なおさらです。
このように考えると、高度プロフェッショナル制度の適切な運用は、労使双方にとって重要だということが分かります。
企業が効果的に高度プロフェッショナル制度を活用するための考え方
今までの時代では、労働意欲を上げるには昇給や昇進が最も効果的でした。しかし、これらは継続的な効果がなく、従業員が現状に満足するとそこで労働意欲の向上はストップしてしまいます。
また景気の低迷で、昇給や昇進をさせたくても原資やポストがなくなっています。お金や地位に働く価値を見いだしていない労働者も増加しており、昇給や昇進はかつてほど労働意欲の向上効果が期待できなくなってしまいました。
優秀と思われる人材を厚遇しても、今の時代は優秀な人材ほど企業を去り、できない優秀ではない人材のみが残る傾向が強まっています。
では、労働者の意欲向上や優秀な人材の確保をするにはどうすればよいのでしょうか?
労働者には、以下の3つのタイプが存在すると言われています。
- 自ら率先して働くタイプ
- 言われたことをするだけで満足するタイプ
- できるだけサボろうとするタイプ
高度プロフェッショナル制度の本質は、①のタイプの従業員を100%生かせるようにすることです。
経営者人材マネジメントから見ると、このタイプの従業員は何もしなくても企業に貢献してくれているため、問題がないように思えるかもしれません。しかし、貢献度が低い同僚や上司と比べて自分の給料や地位に不満を抱いた時、優秀な従業員は転職を考えるようになってしまいます。そのため、まずは優秀な従業員の離職防止が必要となります。それには、高度プロフェッショナル制度が非常に効果的なのです。
なお、企業の強みを高めていくには、一部の優秀な従業員だけに依存するだけでは不十分です。より多くの従業員が成果を出せるようにする必要があることは、言うまでもありません。
高度プロフェッショナル制度は、現時点では対象者を「年収」や「特定の高度な専門業務」に限定しています。しかし、同制度の本質は「個々の従業員の労働意欲が生かせる労働環境」「業務内容と成果と報酬が明確な労働環境」を構築することで、年収や業務内容は関係ありません。経営者は人材育成・管理マネジメントとしていかに同制度を自社に採用していくかを検討し、適切に実施していくことが大切です。
高度プロフェッショナル制度と日本の企業の現状
労働生産性の低さと高度プロフェッショナル制度
日本の生産性の低さは以前から指摘されていますが、公益財団法人日本生産性本部が2017年12月に発表した「労働生産性の国際比較 2017年度版」によると、現在も依然低いまま推移していることがわかります。
さらに日本の時間当たり労働生産性は、OECD(経済協力開発機構)加盟の35カ国中20位、1人当たりでは同21位です。主要先進7カ国(G7)のなかでは最下位です。日本の労働生産性は、1位のアイルランドの約半分しかなく、G7トップのアメリカの約3分の2しかありません。
この労働生産性の低さの原因に、「年功序列型賃金体系」「終身雇用」「成果に関係なく支払われる残業代」など、能力や成果に対して正当な報酬が支払われてこなかったことが挙げられます。一方で、これらの制度は「長期的な視点での人材育成」や「従業員の企業に対するロイヤルティの高さ」を可能にし、日本的経営として大きな成果をもたらしたことも事実です。
しかし今や、その強みは日本を取り巻く環境の変化でむしろ弱みとなってきています。
企業経営を取り巻く環境と高度プロフェッショナル制度
企業経営を取り巻く経済、社会、労働環境は以下のような問題に直面しています。
経済環境
・世界的な不況の継続
・日本の人口減少(日本国内の需要減=経済規模の縮小)
・国際化の進展、国際間競争の激化
・AIやIoTなどIT技術の進化
・個人の価値観の多様化
・所有する満足消費から使用する満足消費への移行
・技術格差が狭まり製品の差別化が困難
・個人の価値観、技術などの変化のスピードが速い など
社会環境
・少子高齢化の進展(労働力減少による人手不足・人材不足)
・女性の活用
・労働・企業に対する価値観の変化
・インターネット、モバイル機器の普及 など
労働環境
・雇用形態の多様化、非正規社員の比率増大
・賃金格差の拡大
・賃金の上昇の鈍化
・長時間労働問題 など
これらに対応するには、さまざまな経営リソースと個別対策が必要です。しかし、その前提となる基本的な必要条件として、以下の2つを満たす従業員の採用・育成が重要となります。
- 自ら考えて行動できる能力のある従業員
- 本質を見極めてそれを解決できる創造性にあふれた従業員
一方で野村総合研究所の「就業意識の変化から見た働き方改革」というレポートによると、1997年から2015年にかけての労働者の就業意識は次の項目で強まっています。
- 会社や仕事のことより、自分や家庭のことを優先したい
- 人並み程度の仕事をすればよい
- たとえ収入が少なくなっても、勤務時間が短い方がよい
- 出世や昇進のためには、多少つらいことでも我慢したい
最後の「出世や昇進のためには、多少つらいことでも我慢したい」の日本語からは、ポジティブな印象を受けるかもしれません。しかし、裏を返すと「寄らば大樹の陰」という安定志向であるとも捉えることが可能です。自らは積極的に行動しないで、ただ企業に寄生していたいという意思が見えます。
他社に横並びの製品やサービスをリリースしていれば一定の売上・利益を確保できていた時代は、過去のものとなりました。今は、多様化した価値観・ニーズをしっかり捉えなければ、売上・利益を伸ばせない時代です。このような時代には自ら考えて、ないものを創造する能力が必要なことは言うまでもありません。
高度プロフェッショナル制度の本質は、これから必要とされる「自ら行動できる人材」を育成するマネジメントに必要な考えだと言えるでしょう。
高度プロフェッショナル制度と労働の小話
論議の「溝」の存在
高度プロフェッショナル制度に関しての議論では、野党と与党との間に溝があることはご存知の方も多いでしょう。この、議論の目的が共有されていないことに本質的な問題が隠されています。
(野党)過労死防止
(政府)高度な専門職を、労働時間規制の対象から除外する
「労働時間規制対象除外=過労死」が短絡的ならば「高度専門職の活躍=労働生産性向上」も短絡的です。
特に「働き方改革」で問題になっている国際比較の労働生産性向上の算出式は、以下の通りです。
労働生産性=GDP/就業者数または(就業者数×労働時間)
労働時間が短縮されれば労働生産性が上がるようになっています。この分母の労働時間の数字を小さくすれば、一気に労働生産性が上がるわけです。法律の改定をすれば済むわけですから、GDPを伸ばすよりも容易でしょう。
ただし、これは見かけだけの問題で、労働の「質」の問題が詐称されてしまいます。
OECDの国際順位では日本は20位で、イタリア15位、スペイン17位(日本生産性本部)より低くなってしまっています。日本人の労働生産性が低いとは、どう考えても合点がいかない方が多いのではないでしょうか。
大切なのは数字の改善ではなく、労働の質や労働者の力を発揮できる労働環境の整備だということを理解しておく必要があります。
なぜ、死ぬまで働くのか?
「労働時間規制対象除外=過労死」という認識は、一部マスコミの過度な報道の影響によるところが大きいです。この報道方法では「なぜ死ぬまで働いてしまうのか」という本質的な問題を隠してしまっています。
普通の人であれば、過労死のニュースが報道されるたびに「そこまで無理する前に、なぜ休まなかったのか」「まわりは止めなかったのか」「他の方法はなかったのか」と思うでしょう。
しかし、どこかのスポーツ選手の危険行為やオウム真理教の事件と同じように、一種の集団催眠的な状況に置かれてしまうと、人間は正常な判断を失います。戦前の日本やドイツもそうでした。
単純に労働時間規制をしても問題解決にはなりません。日本には休めない状況を作り出す「クラッシャー上司」の存在や、組織体質から来る「村社会」特有の悪しき弊害が存在するからです。
日本の労働環境を改善するには労働時間の規制云々ではなく、日本の企業の性質から変えていく意識が大切となってきます。
参照:「なぜ死ぬまで働くのか…「過労死白書」のウラ」(読売新聞社)
フリーランスの存在
フリーランス(個人事業主もしくは個人企業法人)は、そもそもこの議論の蚊帳の外です。労働基準法の適用も受けません。
現在の日本のフリーランスの人口は約1,200万人、労働市場に占める割合は、経済規模が20兆円(日本総給与支払額の10%)を突破しています。(「フリーランス実態調査2018年版」ランサーズ株式会社)
彼らの報酬は自由市場で決定されるため、企業は優秀な人材の引き抜きを防ぐために年収を上げざるを得ません。技術やクリエイティビティで収入が決まるとなれば、学歴や年齢、性別は関係なくなり、勤続年数も意味がなくなります。つまり年功序列の賃金体系が崩れることになるわけです。
このフリーランスの存在と高度プロフェッショナル制度の導入は、従来型の日本の雇用制度や働き方そのものを覆す可能性があります。
果たして高度プロフェッショナル制度は日本の労働文化と適応できるか
アメリカの西部劇の舞台になるような奴隷制の時代でも、奴隷を死ぬまでは働かせませんでした。なぜなら奴隷は貴重な商品であり、死なせてしまっては元も子もなかったからです。日本の江戸時代でも、大名は「百姓は殺さぬように生かさぬように」したと言われています。古典的なマネジメントスタイルです。
現在はさすがにこのような稚拙なマネジメントはありませんが、高度プロフェッショナルの人材には、「スレスレ」まで働かせて利益をあげてもらいたいと考えている経営者も存在するでしょう。
しかし、高度プロフェッショナルの対処となるのは、非常に知的レベルが高く判断能力に優れている人材です。そのような人材が、いつまでも「スレスレ」を容認するはずはありません。酷使される前に他社に移るか、起業して独立してしまいます。
そのため、高度プロフェッショナル制度を導入して長時間労働を強いる企業は、労働者から見放されてしまう可能性が高いです。高度プロフェッショナル制度の導入とともに、日本の労働文化にも変容が求められる時期になったのかもしれません。
企業、政府機関、NPO(非営利組織)のいずれであれ、マネジメントの定義は一つしかありえない。それは、人をして何かを生み出させることである。今後、組織の競争力はこの一点にかかっている。もはや経済学の言う生産資源、すなわち土地、労働、資本からの競争優位は得られない。(中略)
今や唯一の意味ある競争力要因は、知識労働の生産性である。その知識労働の生産性を左右するものが知識労働者である。
(引用:『明日を支配するもの』P.F.ドラッカー著、上田惇生訳、ダイヤモンド社、1999年)
高度プロフェッショナル制度の導入企業が少ない背景
労働者にとっても企業にとってもメリットがあるように思える高度プロフェッショナル制度ですが、導入している企業は非常に少ないのが現状です。
2020年5月4日の朝日新聞によると、同制度の導入企業は制度開始から1年間で10社、適用された労働社は414名に留まっていることが厚生労働省の集計から分かりました。[7]
制度施行前から導入企業は少ないだろうと予想されてきましたが、予想以上に普及が進んでいないのが現状です。では、なぜ高度プロフェッショナル制度は導入しづらいのか。その理由として、以下の理由が考えられます。
- 対象業務が5種類に限定されており、条件制限が厳しい
- 年収1,075万円を超える労働者が少ない
- 制度を導入すれば、社員の年収を内外に示すことになってしまう
- 労使委員会を設置して運用状況を半年毎に報告する義務がある
- 裁量労働制で対応可能
そもそも論として、高度プロフェッショナル制度が適用される労働者は非常に少数となっています。
国税庁の平成29年民間給与実態統計調査によると、年収1000万円以上は民間給与所得者の4.5%。この数字には会社役員も含むので、労働者だけを見ると3%を下回るでしょう。さらに、賞与や手当を抜いた確定額で1,075万円を満たす労働者に絞り込むと、2%を切ることが予想されます。そのうち、労働時間制の適用外となる管理職を除外すれば、適用可能な労働者は1%未満になると予想されます。[8]その中で業務を限定することとなるので、対象となる労働者は一握りでしょう。
条件を満たす労働者が少ない上に、高度プロフェッショナル制度を導入すれば、社内外に年収1,075万円以上の人間がいることが知られてしまいます。企業によっては、これをよく思わないこともあるでしょう。
専門の労使委員会を設置して休日や健康・福祉確保措置を決議した上で労基署へ届け出たり、半年毎に運用情報を定期報告したりと、運用が非常に面倒な点も導入しにくい理由です。裁量労働制の使いにくさを補うために設けた高度プロフェッショナル制度ですが、さらに使い勝手が悪いため、仕方なく裁量労働制を選択する企業が増えてしまっているのが現状です。
高度プロフェッショナル制度が法案成立した経緯
そもそも高度プロフェッショナル制度は、なぜ発案されて成立に至ったのでしょうか。
もともと日本では、長時間労働や有給取得率の低さから、より柔軟な働き方を採用する必要性がありました。それにともない、企業が労働時間を押し付けるのではなく、労働者自身が裁量を持てる働き方にシフトしていくことが重要視されるようになったのです。
労働時間の規制緩和については、2007年の第一次安倍政権、2015年の「脱時間給制度」の創設などでたびたび論争になっていますが、いずれも反対が多く実現には至りませんでした。しかし、2016年に起こった広告代理店の新入社員の過労死自殺をきっかけに世論が高まり、実現に至ったのです。
本来、高度プロフェッショナル制度は、労働者の状況に合わせて労働時間制度を適用するかどうかを判断し、労働生産性を向上させる「労働基準法等の一部を改正する法案」をもとに創設されました。この法案では他にも、裁量労働制やフレックスタイム制の見直しが行われています。
今後の日本が持つべき労働者の姿とは
技術の進化により、ホワイトカラーの労働にもロボット化やAI化が浸透してきています。機械による効率化・人件費の削減が進む中、残業代目的に非効率的な労働をしている従来の日本人労働者は淘汰されていくことは間違いありません。
残業代ではなく成果を出すことを目的とし、本当の意味で企業や社会に貢献できる人材こそが、今後の日本が持つべき労働者の姿だと言えるでしょう。
確かに高度プロフェッショナル制度は残業や長時間労働の懸念が残ります。しかし、現在の技術では、労働時間や健康のAI管理も可能になりました。一人ひとりの健康状況やライフスタイルに合わせて働き方を選択するのは、まさに時代に適した変化だと言えます。
このような働き方を実現するためにも、企業は労働者の成果を適切に評価し、残業時間や長時間労働に縛られない環境づくりをしていくことが大切になります。
高度プロフェッショナル制度の労働者の交通費や通勤手当の扱い
高度プロフェッショナル制度の適用条件は年収1,075万円以上とされていますが、この金額には交通費や通勤手当は含まれるのでしょうか。
厚生労働省の「高度プロフェッショナル制度 わかりやすい解説」には、一定の額で支払われることが約束されている手当は含まれることが明記されています。そうなると通勤手当はもちろん、資格手当や住宅手当なども含まれてくるでしょう。
したがって実際には、年収がもう少し低い労働者にも高度プロフェッショナル制度が適用されることになります。
高度プロフェッショナル制度で企業が求められること
高度プロフェッショナル制度が適用される労働者には、労働時間の制限がありません。労働時間が少ない分には問題はありませんが、労働時間が増えて健康を害することがないよう留意する必要があります。
成果主義の評価制度は無駄な残業を減らせるメリットがある一方で、成果を生み出すための残業を生み出してしまうリスクもあります。また、労働者の間で賃金格差が生まれてしまう可能性がある点にも注意が必要です。
うまく制度を活用するためにも、あらかじめ評価基準を定めた上で、従業員の健康管理を見直す必要があります。そのためには政府発信の資料によく目を通し、制度を理解しておくことが大切です。
高度プロフェッショナル制度の労働時間と健康確保
高度プロフェッショナル制度には社員の健康管理が大切だと何度もお伝えしてきました。しかし、具体的にどんな対策を取ればいいかが分からない経営者の方も多いのではないでしょうか。
厚生労働省の「高度プロフェッショナル制度 わかりやすい解説」を参照すると、企業は高度プロフェッショナル制度対象者の健康を維持するために、以下の措置を講ずることが義務付けられています。[9]
健康管理時間の把握
高度プロフェッショナル制度対象の労働者は、勤務時間や休憩時間、休日などを全て自分の裁量で決定できます。したがって、企業は労働者の労働時間を管理する必要はありませんが、健康を管理するための「健康管理時間」の把握は義務付けられています。
健康管理時間とは、労働者が「事業場内にいた時間」と「事業場外において労働した時間」を合算した時間です。どちらも自己申告制ではなく、タイムカードなどを使用した客観的な方法で記録することが原則となっています。日々の業務時間の記録だけではなく、医師の面接指導を適切に実施するため、1ヶ月あたりの労働時間を把握できるようにしておく必要があります。
休日の確保
高度プロフェッショナル制度では、対象労働者に「年間104日以上かつ4週間を通じ4日以上の休日を与えなくてはならない」と定められています。さらに、決議で休日の取得の手続を具体的に明らかにする必要があります。
選択的措置
労働時間の概念がない高度プロフェッショナル制度では、健康管理時間の把握と休日の確保の他にも、以下のうちのいずれかに該当する措置を講ずることが必要です。
- 勤務間インターバルの確保(11時間以上)+深夜業の回数制限(1ヶ月に4回以内)
- 健康管理時間の上限措置(1週間当たり40時間を超えた時間について、1ヶ月について100時間以内又は3ヶ月について240時間以内とすること)
- 1年に1回以上の連続2週間の休日を与えること(本人が請求した場合は連続1週間×2回以上)
- 臨時の健康診断(1週間当たり40時間を超えた健康管理時間が1ヶ月当たり80時間を超えた労働者又は申出があった労働者が対象)
企業は上記から1つの措置を選択し、実施状況を労働基準監督署へ報告する義務が課せられます。
企業が高度プロフェッショナル制度を開始するまでの道のり
さて、実際に企業が高度プロフェッショナル制度を導入したいと思った場合、どのような手続きをする必要があるのでしょうか。高度プロフェッショナル制度を導入する際は労使委員会を設置したり、労働者との決議を労働基準監督署へ届け出たりと、いくつかのステップを必要があります。
ここからは、その流れについてお伝えしていきます。
労使委員会の設置
まず初めに、企業は労使委員会を設置する必要があります。労使委員会とは、使用者と労働者の代表から構成される委員会のことで、賃金や労働時間などについて意見を述べるために設置するものです。委員会を設置することで、経営者の独断で決議をするのを防ぐ効果があります。
労使委員会で決議する
労使委員会を設置したら、以下の項目について決議していきます。この際、必ず委員の5分の4以上の多数による決議が必要です。
- 対象業務
- 対象労働者の範囲
- 健康管理時間の把握
- 休日の確保
- 選択的措置
- 健康管理時間の状況に応じた健康・福祉確保措置
- 同意の撤回に関する手続
- 苦情処理措置
- 不利益取扱いの禁止
- その他厚生労働省令で定める事項
気が遠くなるほど項目が多いですが、これら全てについて話し合った上で決議をしていきます。
企業が労働基準監督署へ提出・対象労働者の同意
使役委員会で無地の決議がなされたあとは、決定事項を労働基準監督署へ届け出ます。届出がないと高度プロフェッショナル制度は導入できませんので、必ず忘れずに行っておきましょう。
また、対象労働者に高度プロフェッショナル制度を適用するには、本人から書面で同意を得る必要があります。
企業はあらかじめ制度の概要や使役委員会の決議内容、同意した場合の賃金制度・評価制度などを書面で明示し、労働者の署名を得てください。この時、「同意をしなかった場合に不利益取扱いが行われないこと」「同意の撤廃が可能なこと」をしっかりと明記する必要があります。
対象労働者を対象業務に就かせる
上記までのステップが完了すれば、実際に対象労働者を高度プロフェッショナル制度で業務に就かせることが可能となります。
ただし対象労働者は、同意の対象期間内であればいつでも同意を撤廃できます。
高度プロフェッショナル制度の本質を企業に活かしてください
高度プロフェッショナル制度は、「労働者とってデメリットが多い制度」「人件費削減になる企業にしかメリットのない制度」だと思ってはいませんか?
同制度の本質はそういった点ではありません。労働者の働き方の改善や生産性の向上など、従来までの日本の労働環境を改善することが目的の制度となっています。本質を理解して導入すれば双方にメリットがあり、企業がこれからの時代を生き抜く経営力の強化も可能となります。
本記事を参考に、ぜひ同制度の本質を人材マネジメントに生かすことをご検討ください。
[adrotate group=”15″]
参照
[1] [3] [9]高度プロフェッショナル制度 わかりやすい解説(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000497408.pdf
[2]https://www.bengo4.com/c_5/n_2857/
[4]https://www.jpc-net.jp/intl_comparison/intl_comparison_2017_press.pdf
[5]https://www.lancers.co.jp/news/pr/14679/
[6]http://biz-journal.jp/2018/05/post_23372.html
[7] https://www.asahi.com/articles/ASN5364NFN4XULFA03K.html
[8] https://www.hrpro.co.jp/agora/6313
「ワーク・ライフバランス」では?
https://work-life-b.co.jp/profile/yoshie_komuro.html
[adrotate banner=”36″]