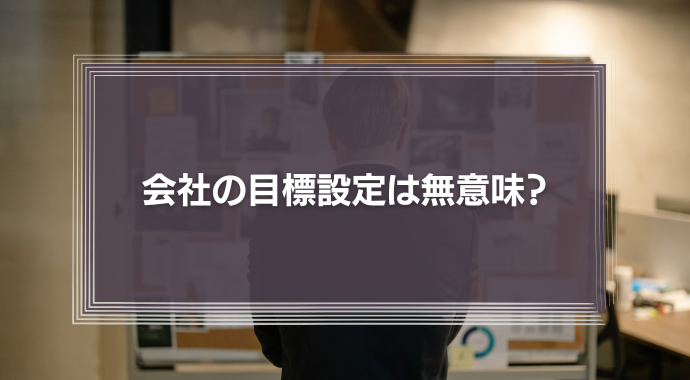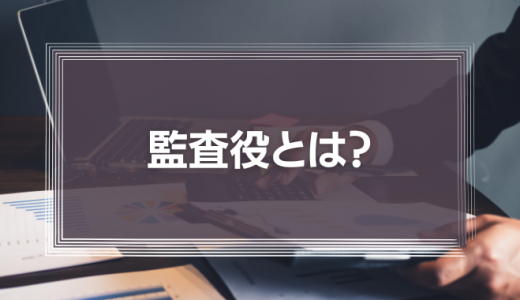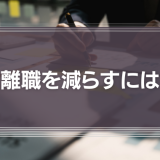「成果の話をしよう」というと、好ましい反応が帰ってくることはあまりない。
実際、「窮屈なのはちょっと……」という方のほうが多いかも知れない。
逆に「成果とは関係ない、職場の謎ルール」の方に、会社は熱心に取り組んでいるようだ。
「新入社員は勤務時間外のイベントにも必ず出席」(50代男性)
「最初数年、新入社員は社屋から離れたスペースに駐車する。近くに止めると、遠回しに上司から嫌みを言われる」(50代男性)
「先輩の遅刻は指摘しない」(40代女性)
「役職の高い順から退社」(50代男性)
「職場のコーヒーは1日2杯まで」(50代男性)
「7月まで冷房不可」(30代男性)
「エアコンは除湿のみ」(40代女性)
「エレベーターを降りたら1階に戻す」(50代男性)
「社内の人にも『お世話になります』と挨拶」(50代男性)
「メール送信前に『メールを送る旨』を電話する」(40代男性)
「社長が来たらゴミ箱を隠す」(30代女性)
「社員旅行の候補地に関して社内アンケートを採るが、いつも社長が行ったことのないところになる」(50代男性)
「上司が言い出すまで昼食不可」(40代男性)
「社長が宴会で挨拶したら、それについて後日レポートを提出」(30代男性)
「懇親会は正社員のみ」(40代男性)
「アルバイトは室内履き持参不可」(30代女性)
「契約社員は電話使用不可」(30代男性)
確かにちょっと笑ってしまうようなルールが設定されている会社があることは事実だ。
だが、「成果の話」は忌むべきものなのか、といえば、当然そうではない。
成果に関する決め事があるからこそ、「変なルールに惑わされず、成果に打ち込むことができる」のだ。
実際、「自由」「自律」を標榜するGoogleは、社員に厳格な「目標管理」が設定されている。
グーグルの業績管理システムは常に目標設定から始まった。2000年代はじめ、グーグルの取締役だったジョン・ドーアは、インテルが使って大成功を収めていたある手法を目にし、グーグルに導入した。
それがOKR(Objectives and Key Results:目標と主要な結果)だ。
結果は具体的、計測可能、検証可能でなければならなず、すべての結果達成すれば目標を成し遂げたことになる。
逆に、「成果についてのルールが欠けている組織」は、どこかで必ず、構成員の揉め事や、機能不全を起こす。
\ \ 社員を増やしたのに業績が伸びないのは、社員の能力の問題ではありません! / /
>>【マンガで学ぶ】成果に直結するマネジメント理論識学の全容 無料プレゼント中
<<あわせて読みたい>>
ジョン・コッターの『企業変革力』まとめ【組織変革を成功に導こう】
目次
成果についてのルールがあいまいな組織が多い
「成果についてのルール」と言えば、私も強く記憶していることがある。
昔、中小企業向けの「人事評価制度構築」のプロジェクトに携わっていた時の話だ。
私が在籍していたコンサルティング会社は、
「評価基準を定量的にする」
「昇進、昇格の条件を明示する」
「評価基準を社員に公開する」
という評価制度をつくるようにクライアントに勧めていた。
「評価に実効性を持たせるには、現場の納得感が必要」だったからだ。
さて、私が初めてこの話を上司から聞いたとき、私は素直に
「良い評価制度だ」
と思った。
自分の場合、自分がなにで評価されるかを知ることは重要だったし、何より
「なにが評価されるべきか」自分で決められるならば、仕事を頑張れると思ったからだ。
ところが。
現実はそう甘くない。
このコンサルティングの現場に初めて入ったとき、
「これは……何という難易度の高い試みだろう」
と、感じたのだ。
中でも最も戸惑ったのは、
「ルールを明確にしたくない」という管理職と、そして社員たちもが、あまりに多いことだった。
定量化した会社の目標を嫌がる社員が多いワケ
例えば「本年度の営業職の昇進の必要条件」として、
- 売上目標の達成
- クロスセル◯件
- 企画書の承認◯件
- 勉強会での発表◯件
- 課題図書◯冊について読み、期日までにレポートを提出する
- 遅刻ゼロ(公共交通機関の遅延など、やむを得ない状況を除く) といった条件を、誰かが挙げる。
すると、殆どの場合、一部の人から
「売上目標達成は良いが、クロスセルは運もある。条件に入れるのはおかしい」
「企画書の承認は恣意的だ」
「遅刻ゼロは厳しすぎないか」
などと「猛反対」がある。
「では、代案はありますか?」と聞くと、
彼らの殆どは、
「ケースバイケースだ」
と答えるのだ。
もちろん、ケースバイケースであっても構わない。
だが、全てが「ケースバイケース」では、結局なにも決めていないと同じである。
私はこれが不思議でしょうがなかった。
「協力して、皆で成果を明確にしたほうが、頑張れるじゃないか」と思っていたのだ。
会社というのは、成果をあげるべき場所であり、成果を明確に定義しておくことは重要なはずだ。
ピーター・ドラッカーも「成果をあきらかにせよ。」と言っているではないか。
マネジャーたるものは、上は社長から下は職長から事務主任にいたるまで、明確な目標を必要とする。目標がなければ混乱する。
目標は自らの率いる部門が挙げるべき成果を明らかにしなければならない。
他部門の目標達成の助けとなるべき貢献を明らかにしなければならない。
他部門に期待できる貢献を明らかにしなけれればならない。
P・ドラッカー マネジメント エッセンシャル版 ダイヤモンド社
だが、彼らははっきり言わないまでも、
全てにおいて「ルールはできる限りあいまいにしておきたい」としていた。
もちろん、管理職も
「評価基準を明確にしたくない」
「昇進の基準を明確にしたくない」
「ケースバイケースにしたい」
と、社員と同様だった。
私は困って、上司のコンサルタントに相談した。
「なんであの人達は、成果を決めることに反対するんですかね。」
上司は言った。
「安達さんは、若いからわからないかも知れないけどね、歳を取ると、成果を出せる自信がなくなってくるんだよ。
自分の能力がこれくらい、ってわかってくるし。」
「……。」
「でさ、彼らだってわかってんだよ。自分が昇進の対象じゃないって。でも「明確」にされたら、もう最後のプライドまでズタズタだろう?だから、必死に抵抗するわけだ。」
「……。」
「でも、アンケートで「どうしたら評価されるのかわからない」という意見、多いじゃないですか。」
「アンケートに「どうしたら評価されるのかわからない」って書いておけば、自分が成果を出していなくても、人のせいにできるだろう?」
「嘘ってことですか?」
「嘘といえばウソ、ホントと言えばホントだよね。」
「でも、一般の社員だけじゃなく、管理職ですら反対してますが、あれは何なのでしょう?」
「彼らは共犯だよ。部下に「これだけやったら、昇進させてあげる」と約束できないから、
あえて昇進の条件を曖昧にしておくのさ。」
「成果を上げた部下を昇進させることが出来ない上司なんて、いる意味はないじゃないですか。」
「そうだよ。だから決めたくないよね。明確な昇進のルール。それを何とかするために、我々は経営者に雇われるんだよ」
それ以来、私は無数の企業の成果測定に携わり「ルールのない組織」と「ルールがしっかりしている組織」を両方見てきた。
そして確かに、私が見た「停滞している組織」の殆どは、「成果に関するルール」が非常に曖昧、かつ恣意的だった。
実際、「成果に関するルールのない組織」は、業績の良いうちは良さそうに見えるのだが、少し業績に陰りが出てくると、途端に人間関係の
フラストレーションが爆発して、簡単に崩壊する。
逆に「ルールのありすぎる組織」は、動きは遅く、社員のイライラもあるのだが、多少の業績の上下動に関して強い傾向にある。
したがって「永く続く組織」を作るのであれば、経営者は必ず「成果に関するルールの策定」を真剣に行う必要がある。
<<あわせて読みたい>>
経営理念を従業員に理解させることは無意味!マネジメントのコツは適材適所
まとめ 成果を評価するルールをあいまいにしてはいけない
うだつの上がらない会社は「成果を明確にしたくない社員」と、「成果をあげた部下を評価できない上司」が結託している。
長期的には、それが彼らの待遇を悪化させ、ついには会社を崩壊させるとしてもである。
経営者、マネジャー、そして一般社員に至るまで、「成果」は会社が生き残るための絶対的条件だ。それをごまかし、有耶無耶にしてはならない。
たとえそれが社内に一時的に摩擦を起こしたとしても。