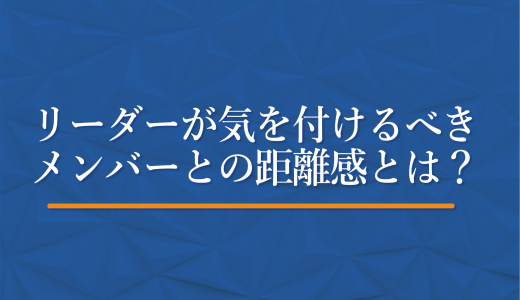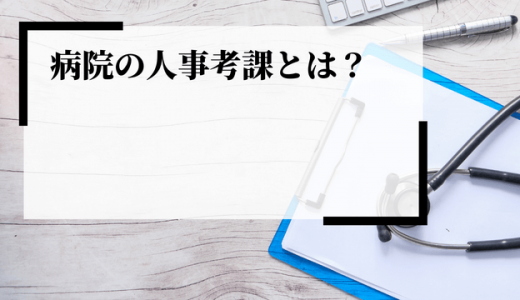仕事の思い出として、その振る舞いを忘れられない人がいる。
彼の社内での役割は、ちょっと変わっていた。
中小企業は、No.2が営業か製造部門であることが多いが、彼は人事的ポジションだった。それも、従業員のモチベーションに関わる担当だった。
こう言うと難しく聞こえるが、単純に言うと、カウンセリング役。
いや、率直に言うと洗脳担当とでも言うべきだろうか。
要するに、会社の方針にあわない人物に対して、考え方の転換を迫ったり、不満を抱えている人物に対して話を聞きにいき、場合によっては説得を試みる役割だった。
もちろん、普通に考えれば、こんな役割の人を中小企業が抱えておくわけがない。
だが、経営者が「ビジョナリー・カンパニー」にハマっており、ビジョンを中心とした経営の推進役として彼を選抜した、というのが実際だ。
彼はコミュニケーション能力が高く、社内で一目置かれていた人物で、仕事もできたが、時が経つうちにその人の評判は二極化していった。
例えば、彼に好意的な人々は、こう言った。
彼の言っていることは心に響いた。
厳しい言い方をされたが、言っていることはその通りだと思う。彼に感謝している。
一方で、彼を毛虫のように嫌う人々もいた。
曰く、彼ほどの偽善者はおらず、彼のいうことは経営者と保身のためである。
「あなたのため」と彼は言うが、実は彼は単なる経営者のイヌだというのだ。
彼はその人のことを思って言うのではなく、経営者にチクるために、その人から本音を引き出そうとしているだけなのであると。
彼を嫌っていた(そして彼に嫌われた)人々は、会社から次々と消えていった。
ある人は退職勧奨され、ある人は会社と散々揉めた挙げ句、自主的に退職していった。
このように同じ人物が、このように大きく別れる評価をされるのは決して珍しいことではないが、あまりの二極化ぶりに、特にその話術について、私は非常に興味を惹かれた。
<<あわせて読みたい>>
メタバースとは?メタバースの語源や意味、具体例をわかりやすく解説!
DXとは?デジタルトランスフォーメーションの意味や定義をわかりやすく解説
目次
彼はどのように人に対峙していたのか
彼は非常に用心深い人物だった。
飲み会、昼食中などはおろか、ほとんどどんな場でもほとんど自分の意思を見せなかった。
といっても、彼は決して寡黙ではなかった。
むしろよく話し、よく人とコミュニケーションをとっていた。
だがよく聞くと「意見のように見えること」は言うが、それは殆どの場合、本音とは呼べないようなもので、
「彼の本当の意図がどこにあるのか」
「何を考えているのか」
については、ほとんど手がかりらしい手がかりを与えてくれなかった。
それゆえ、本人からは、説得を試みる手法についての話は殆ど聞けなかった。
だが、様々な人の話を聞くと、彼が何をしていたのかおぼろげながらわかってきた。
端的に言うと、彼はまず、「ビジョンを実践する」という名目で、高めの目標と、かなりの量の仕事を与える。
具体的には「当社のビジョンの一つは、人は高い目標に向かって一生懸命仕事をすることで成長する、だぞ。」
とささやく。
そして、本人が疲弊してきたところで、手を差し伸べて説得にかかる、と言う寸法だ。
当時は気づかなかったが、実はこれは「マインド・コントロール」の方法に酷似している。
本人の主体性を奪い、操り人形やロボットに仕立て上げようと思えば、常に情報過剰な状態に置き、脳がそれらの情報処理で手いっぱいになり、何も自分では考えられない状態にしてしまえばいいということになる。(中略)
学習や自己啓発、修練、真理の探究を目的として、早朝から深夜まで取り組みを行わせ、話をしたり、講義を聞いたり、集会をしたりといったことが延々と続けられる。
(中略)
欠乏と不安の極限状態に置いて、精神的な抵抗力や批判的に考える力を奪ったうえで、いよいよ核心に踏み込んでいく。そこで行われるのは、あなたにも救われる道があると語りかけることだ。我々の仲間になって信念を同じくすれば、すばらしい意味をもつ人生が始まると、希望を約束するのだ。
(岡田尊司. マインド・コントロール 増補改訂版 文藝春秋)
彼がマインド・コントロールの手法を知ってやっていたとは考えにくいが、結果的にこの方法がうまくいきやすい、という確信は持っていたにちがいない。
事実、仕事になれない新人や、中途の若手に大きな効果を上げていたのは、慣れない仕事でより疲弊していた人々のほうが、効果が高かったからなのだろう。
ビジョナリー・カンパニーはカルトと酷似している
ところで、ここに一冊の本がある。
タイトルは「ビジョナリー・カンパニー」。上の会社の経営者がハマっていた本だ。
この本は、ビジョナリー・カンパニー(一九五〇年以前に設立され、業界内で卓越し、当初の主力商品(またはサービス)のライフ・サイクルを超えて繁栄している企業群)
の繁栄の源泉は、「ビジョン」であるという主張を検証した著作だ。
その中で、私が特に面白いと思ったのは、ビジョナリー・カンパニーとカルトには、共通点が多いという発見だ。
調査チームの会議の席上で、調査助手のひとりが感想を話した。「これらの企業につとめるのは、きわめて同質的なグループや組織に加わるようなものだと思える。自分に合っていなければ、入らない方がいい。
企業の考え方を心から信じて、献身的になれるのであれば、本当に気持ちよく働けるし、成果もあがるだろう。たぶん、こんな幸せはないと思えるだろう。
しかし、そうでないのなら、たぶん失敗し、みじめになり、居所がなくなり、いずれ辞めていくことになる。病原菌か何かのように追い払われる。白か黒かがはっきりしているのだ。
仲間になれるのか、仲間外れにされるのか。どちらかであり、中途半端ということはない。カルトのようだと言えるほどだ(中略)
ビジョナリー・カンパニーに比較対象企業より顕著にみられる特徴のなかに、カルトと共通した点が以下の四つあることがわかった。
・理念への熱狂(『利益を超えて』の章を参照)
・教化への努力
・同質性の追求
・エリート主義
(出典:ジム コリンズ;ジェリー ポラス. ビジョナリー・カンパニー 時代を超える生存の原則 日経BP社)
そうだ。
上述した「ビジョナリー・カンパニー」にハマっていた経営者は、自分の会社をカルト化しようとしていた。
腹心の人事担当は、その伝道師だったのだ。
そう考えると、「考え方の合う」人々が、その人事担当者を慕い、「考え方が合わない」人々が、強く反目する理由もわかる。
実際、ビジョナリー・カンパニーにも、次のようにある。
カルト主義の企業には、採用にあたってか、入社後の早い時期に、基本理念に合わない社員を厳しく選別する傾向がある。
そして、残った者には強烈な忠誠心を吹き込み、行動に影響を与えて、社員が基本理念に従い、熱意を持って常に一貫した行動をとるようにする
「病原菌のように追い払われる」社員としてはたまったものではないが、「ビジョナリー・カンパニー」とはそういう存在なのだ。
結局、「ビジョナリー・カンパニー」を目指した会社はどうなったか?
さて、話を戻そう。
結局、上の会社はどうなったのか。
なんと、カルトを推進していたNo.2の彼は、早々に会社を辞めてしまった。
彼は本音を最後まで語らなかったが、どうやら社長と考え方が合わなくなっていったようだ。
後で聞いた話だが、真相はこうだった。
社長から、『ビジョンの徹底を図れ』と言われて動いた彼は、ビジョナリ・カンパニーににかかれていることそのままに、ビジョンを体現しない社員をひたすら排除した。
そして、排除の結果、面白いことに「ビジョンに合わない社員」だけではなく、「ビジョンに共感はしているが、排除の論理を嫌う社員」まで辞めてしまったのである。
「ひどい辞めさせ方をしている」
「できない人を排除するのはやめてくれ」
そう言い残して、辞めていった人は数多い。
そして、その中に社長の腹心も何人か含まれていた。
そのことで、社長は彼を責めた。
「俺が排除したいのは、ビジョンに共感しないやつだけだ。」と。
だが、彼は言った。
「私は社長の指示どおりやっただけです。ビジョンに共感しない人物は辞めてもらいました。ただ、他の人物が辞めてしまったのは、私に「ビジョンに共感しない人物は排除せよ」と言った社長の責任では?」
社長は憤慨した。
「言い方や、やり方がまずかったんだろう。」
「社長、覚悟を決めてください。ビジョンに従って人を排除する、ということは、社長の好きな人だけを残すことはできない、ということです。実際、ビジョナリー・カンパニーには、カリスマ経営者は不要だとあります。」
そして、彼は言った。
「社長、社長が個人的な好き嫌いで会社を運営しようとするならば、ビジョンはもう不要かと思います。私も役目を終えました。」
そして彼は、会社を去り、この会社は「ビジョナリー・カンパニー」の追求を止めた。
「排除」でチームを作ることは不可能である。
結局、私がこの話から得た教訓は
「排除の論理で、チームを作ることはできない」
という一点である。
結局、皆が本当に共感するビジョンがあれば、伝道師など必要なく皆がそれを実現したくなるはずだ。
むしろたかだか100名程度の中小企業で「ビジョンに共感しない人の排除」が主な作業になってしまった点で、そのビジョンの妥当性、正当性には疑問が残る。
多くの経営者は、「従順な人物」「できる人」を選別し、「扱いにくい人物」「できない人物」を排除したがる。
会社が小さいうちは、それでもよい。
だが、会社を真に卓越させるのは、「扱いにくい人物」「できない人物」をも包含する、仕組みとビジョンなのだ。
そのことを、「ビジョナリー・カンパニー」を作ろうとして失敗した会社は、教えてくれる。
まとめ ビジョナリー・カンパニーが優れているとは限らない
最後に余談だ。
ビジョナリー・カンパニーが真に優れているのか言えば、データ上は、実はそうではない。
例えば、ノーベル経済学賞を受賞した、プリンストン大のダニエル・カーネマンは、ビジョナリー・カンパニーは、統計的には虚構であると述べる。
『ビジョナリー・カンパニー』で調査対象になった卓越した企業とぱっとしない企業との収益性と株式リターンの格差は、大まかに言って調査期間後には縮小し、ほとんどゼロに近づいている。
トム・ピーターズとロバート・ウォーターマンのベストセラー『エクセレント・カンパニー』で取り上げられた企業の平均収益も、短期間のうちに大幅減を記録している。
(ダニエル・カーネマン ファスト&スロー)
また、上述した会社のように、ビジョンの浸透の名のもとに、マインド・コントロールまがいの手法を使う人事担当を暗躍させる会社も存在する。
ビジョナリー・カンパニーが書かれたのは1995年。今ではすでに25年前の書物であり、新しいテクノロジーの出現によって、世界は当時から大きく変わった。
「ビジョナリー・カンパニー」で取り上げられていた会社群も、現在では平凡な会社に成り下がってしまったところも多いだろう。
「ビジョンの浸透」を会社の経営者が採用することについては自由である。
だが、それは魔法の杖ではない。
卓越した会社がそれで全て説明できるわけでもない。
おそらくそれは単なる「カルト的な文化が好きだ」という、嗜好の問題なのだろう。
<<あわせて読みたい>>